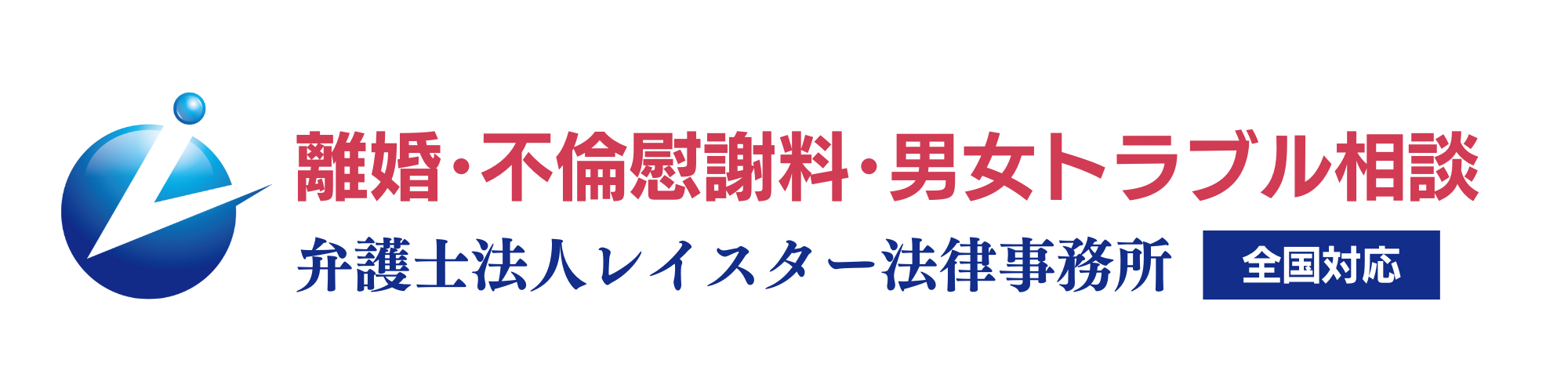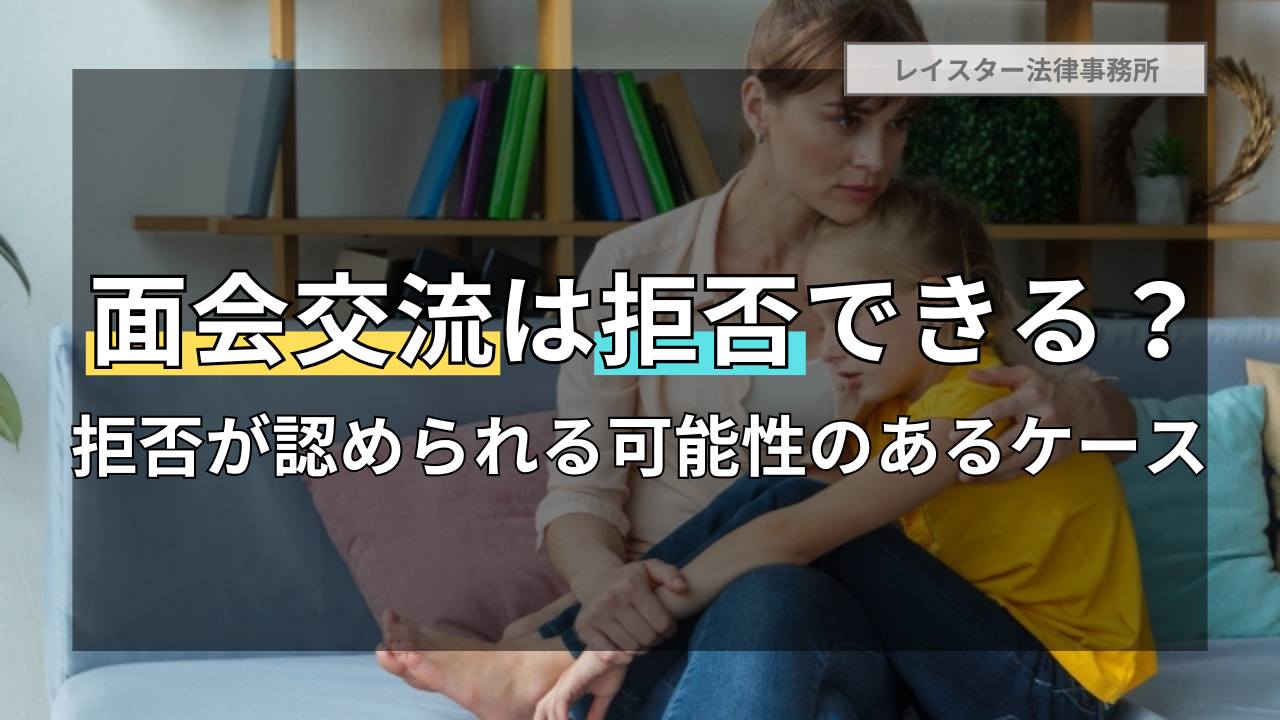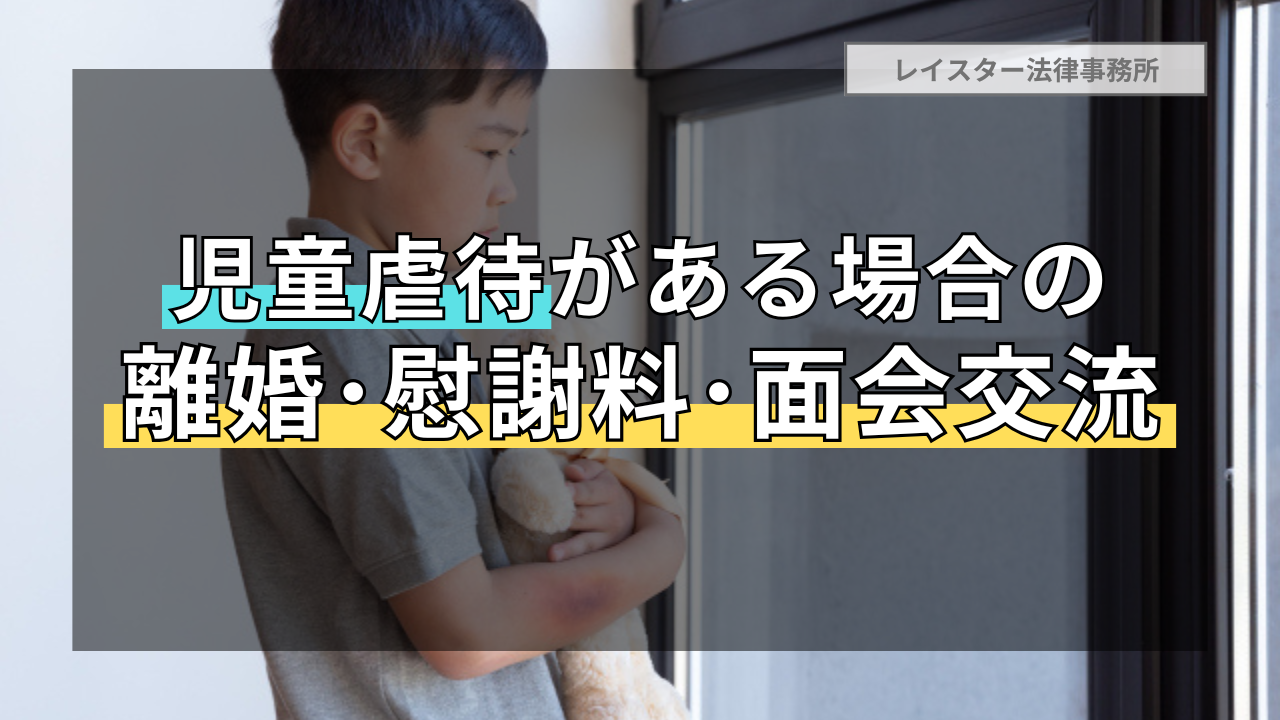1.面会交流についての基礎知識
⑴面会交流とは

面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方(別居親)が子どもと会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
面会交流は別居親の権利であるとともに、別居親と離れて暮らしている子どもの権利でもあると考えられています。
面会交流は子どものために重要な権利であると考えられており、法律上も「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流・・・について必要な事項は、その協議で定める。」と規定されています(民法766条、民法771条)。
⑵別居親は子供と自由に会うことはできない
子供と離れて暮らしている別居親も、離婚するまでは子供の親権者であることに変わりはありません。
ただし、既に別居の状況に至っている以上、子供は子供と生活をしている同居親の事実上の監護の下で、ひとまず平穏な生活状況に至っています。
そのため、別居親が同居親に無断で子供と自由に会ったり、子供を制限なく連れ回したりすることは、基本的には認められません。
まして、別居親が同居親に無断で子供を連れ去った場合には、状況によっては、未成年者略取罪(刑法224条)が成立する場合もあります(最高裁判所決定平成17年12月6日)。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
離婚後の場合も同様に、同居親と別居親のいずれに親権があるとしても、別居親が同居親に無断で子供と会ったりすることは、基本的には認められません。
別居親が離れて暮らす子供と会うためには、まずは同居親との間で話し合いを行う必要があります。
⑶面会交流に関する事項の決め方
別居親と子供との面会交流を実施するかどうかや、面会交流の頻度・時間・受け渡し場所などの条件(面会条件)は、同居親と別居親が話し合って決めていくこととなります。
同居親と別居親が直接話し合うことができない状況にある場合や、話し合いをしたものの話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、調停委員を間に挟んで、話し合いを進めることとなります。
面会交流調停を通じて話し合いをしてもなお話し合いがまとまらない場合には、最終的には、家庭裁判所が面会交流の実施の是非や面会交流の条件(面会条件)を審判という形式で決定することとなります。
また、一度は面会条件について決定したものの、子供の成長に合わせて面会交流の内容を変更したくなった場合には、再度同居親と話し合ったり、面会交流調停・審判などの手続きを経ることで面会交流の条件を変更することも可能です。
⑷夫から面会交流を求められた場合に考えるべきこと
夫婦は様々な理由で別居に至ります。
夫との性格の不一致や価値観の違いに限界を感じて離婚を決意して別居に至ることもあります。
気性の激しい夫の暴言・モラハラやDVに耐えかねずに、苦しんだ末に意を決して別居を開始することもあります。
また、夫による子供の虐待をどうしても辞めさせることができずに、子供を守るためには夫と子供を物理的に離すしかないと覚悟を決めて、別居に踏み切ることもあります。
夫と別居した後は、夫との同居生活の苦しみから逃れ、夫の介入のない子供との新たな生活がスタートします。
ただ、別居や離婚に至った理由がどうであれ、別居中の夫・離婚した元夫から子供との面会交流を求められることはよくあります。
その場合、面会交流には常に応じなければならないのでしょうか。
2.面会交流に関する家庭裁判所の考え方

法律上、面会交流に関する事項を取り決める際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定められています(民法766条後段)。
家庭裁判所も、面会交流に関する事項(面会交流を実施するべきかどうかや面会条件など)の話し合いや取り決めに関して、子供の利益を最優先に考えています。
そして、家庭裁判所は、面会交流の実施は子の福祉に資する(子供の健全な成長・発展のためには面会交流を実施することが望ましい)と考えています。
つまり、家庭裁判所は、子供の利益を最優先に考えた結果、面会交流は原則として実施されるべきであるという考えに基づいて運営されています。
そのため、家庭裁判所は、どうにか面会交流が実施される状況に至るべく、同居親に面会交流の実施に協力するよう働きかけたり、面会交流の実現のために様々な提案をしてきたりします。
例えば、同居親の感情的な都合(別居親が憎い、別居親に嫌がらせをしたい、別居親に仕返しをしたいなど)は面会交流の実施を拒否する理由として家庭裁判所は受け付けてくれません。
「子供にとってはいいかもしれないけれど、私は会わせたくない!」という理由は、家庭裁判所は認めてくれません。
同居親がそのような理由で面会交流の実施を拒否していたとしても面会交流に関する話し合いは終わりませんし、延々と面会交流調停での話し合いを長期間続けた末に、最終的には面会交流の実施及び面会条件を定める審判が出されることに至る可能性があります。
3.面会交流の拒否を巡って争いとなり得る問題点
⑴「子供が会いたくないと言っている」という理由での面会交流の拒否

子供の年齢にもよりますが、一般的に子供が小さいうちは、子供が会いたくないと言っているという理由で、家庭裁判所が面会交流の拒否を認めてくれることはあまりありません。
まず、別居親から、子供が会いたくないと言っていることが真実であるかどうかが問題視されることがよくあります。
その場合は、家庭裁判所の調査官が子供と面談をして子供の心情を調査することもあり、その結果、子供が別居親と会いたくないと発言しているという事実が明確に示される状況になる場合もあります。
しかし、子供が小さい場合には、子供が同居親の心情に配慮して、別居親とは「会いたくない」と発言することもよくあることであり、家庭裁判所もそのことを前提として考え、子供の言葉の通りに捉えてくれないことも多いです。
また、子供と別居親の親子関係は生涯不変のものです。
そのため、子供が別居親に会いたくないと発言をしている状況であったとしても、そのことはむしろ子供と別居親との関係を改善するためにどのような行動が必要となるのかなどといった、面会交流の実施に向かう方向で話が進められることも多いです。
そのため、当事者間で合意が成立せずに家庭裁判所が面会交流に関する事項を審判で決めることとなった場合には、本当に子供が会いたくないと言っていたとしても、面会交流の実施及び面会条件を定める審判が出されることに至る可能性は十分にあります。
他方、後述するように、子供が一定程度の年齢に達しており、子供の別居親を拒絶する心情が強い場合には、面会交流の拒否が認められる場合もあります。
⑵別居親が面会交流の条件に違反したことを理由とする面会交流の拒否

面会交流の円滑な実施には同居親と別居親との間で最低限度の信頼関係が築かれていることが必要です。
面会交流の実施の前に事前に同居親と別居親との間で取り交わしていた面会条件(時間や場所など)に別居親が違反したこと(例えば終了の時間に戻って来なかったなど)は、この同居親と別居親との間における信頼関係を破壊する行為です。
事前に明確に取り決めた約束事を守れない別居親に対して大切な子供を渡して面会交流をさせることに不安を感じることもあるものでしょう。
ただし、その違反の程度が軽微であるとか、誤解や無知に基づくものである場合とか、別居親が以後違反しないことを約束している場合などの場合には、面会交流の拒否までは認められないでしょう。
この場合は、むしろ今後別居親がどのような約束事を守るのであれば面会交流の実施に協力することができるかという方向で話し合いが進められることとなることが多いです。
他方、例えば別居親が面会交流の機会に乗じて子供を連れ去った場合や、連れ去ろうとした疑いが生じる程度に重大な違反があった場合(終了時刻に戻って来ずに連絡も取れないまま長時間が経過した場合など)には、そのことを理由に以後の面会交流の実施の拒否が認められる場合もあります。
⑶面会交流を実施した上で生じた問題点を理由とする面会交流の拒否
例えば、面会交流を実施した後に子供が疲労困憊になって帰ってきて学校生活に支障が生じたとか、面会交流の実施から帰宅した子供が精神的に不安定な様子を見せていたなどといった事情が生じる場合があります。
しかし、このような事情についても、面会交流の拒否までは認められず、むしろ今後どのような面会条件であれば面会交流の実施に協力することができるかという方向で話し合いが進められることとなることが多いです。
⑷別居親と直接会いたくないという理由での面会交流の拒否
子供が小さい場合には、面会交流に際して、同居親と別居親が対面する形で子供の引き渡しが行われることが通常の形です。
ただ、夫婦の婚姻関係が破綻した事情によっては、絶対に別居親に会いたくないと考えることも珍しいことではありません。
しかしながら、そのような「自分が配偶者・元配偶者と会いたくない」という事情は面会交流を拒否が認められる事情とまでは考えられていません。
その場合は、どのような工夫をすれば同居親と別居親が直接対面することとならずに面会交流を実施することができるのかという話し合いに進んでいくことが多いです。
例えば、調停委員から子供の引き渡しを行ってくれる親族などの協力者がいないか聞かれたり、面会交流を支援している第三者機関の利用などを打診されてそのような第三者機関の支援を利用する形での直接交流の実施に協力できないかどうかの検討を求められたりすることはよくあります。
4.面会交流を拒否できる場合

ただし、面会交流を実施することが子の福祉に反する(子供のためにならない)と考えられる事情が存在している場合もあります。
そのような面会交流を拒否する正当な事情が存在している場合であれば、家庭裁判所は、むしろ子供の利益を最優先に考えた結果、面会交流(特に直接の交流)を実施しない方向で話を進めてくれます。
面会交流を完全に実施しないというところまでは難しいとしても、例えば、子供との直接の交流の実施を求める別居親に対して、間接交流(手紙や電話のやり取りなど)や、片面的な間接交流(子供の写真を送るなど)で合意するよう働き掛けてくれたりする場合もあります。
面会交流を拒否する正当な事情が存在しているにも関わらず別居親が納得せずに子供との直接の交流を求め続けたとしても、その場合は最終的には家庭裁判所により面会交流の実施を否定する審判が出される可能性があります。
このように、面会交流を実施することが子の福祉に反する(子供のためにならない)と考えられる事情が存在している場合であれば、面会交流を拒否できますし、むしろ子供のために拒否するべきともいえます。
具体的には、以下のような場合であれば、面会交流の拒否が認められる場合があります。
- 別居親が面会交流中に子供を虐待するおそれがあるケース
- 別居親が面会交流の機会に乗じて子供を連れ去るおそれがあるこケース
- 子供が面会交流の実施を強く拒絶しているケース
- 同居親が面会交流の実施に協力しないことに合理的な理由があるケース
⑴別居親が面会交流中に子供を虐待するおそれがあるケース
別居親が面会交流の最中に子供に対して虐待(暴言や暴力)を振るう可能性があるのであれば、面会交流を実施するべきではないことは当然です。
この場合は、家庭裁判所に対して、別居親が過去に子供に対して虐待をしていたことを証拠に基づいて説明して分かってもらったり、別居開始後の相手の言動からして相手が面会交流の実施中に子供に対して虐待をする具体的な危険性が存在していることを分かってもらいましょう。
⑵別居親が面会交流の機会に乗じて子供を連れ去るおそれがあるケース
別居親が面会交流の機会に乗じて子供を連れ去るおそれがある場合には、別居親に子供を会わせるわけには行きません。
上述したように、そのような子供の連れ去りは、状況によっては、未成年者略取罪(刑法224条)が成立する場合もあります(最高裁判所決定平成17年12月6日)。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
ただ、同居親がそのような抽象的な危惧感を有しているに過ぎないという状況の場合は、面会交流の拒否までは認められない場合もあります。
また、別居親による連れ去りの現実的な危険性が低い場合には、第三者機関の付添型支援を利用して連れ去りのリスクを回避することで直接交流の実施に協力できないかどうかを検討するよう求められる場合もあります。
⑶子供が面会交流の実施を強く拒絶しているケース

子供が別居親のことを強く拒否している状況では、子供の意思を無視して別居親との面会交流の実施を約束するわけにはいきません。
特に子供の年齢が大きく、自らの意思で別居親との交流を完全に拒否していると考えられる場合には、同居親としてもやりようがないでしょう。
その場合は、まずはその子供が別居親を拒否している理由を検討し、それを改善するために何が必要となるのかが話し合われることが多いです。
ただ、どうしても子供の拒否が強く、その改善もできそうもない場合には、子供自身の意思・意見を尊重して現時点では面会交流を拒否し、一定程度期間を空けて再度検討をするという方向となることがあります。
⑷同居親が面会交流の実施に協力しないことに合理的な理由があるケース
同居親が面会交流の実施に協力しないことに合理的な理由がある場合も、面会交流の拒否が認められる場合があります。
例えば、同居親が別居親による激しい暴言・モラハラやDVの被害に遭っており、その被害から逃れるために別居を開始した上、別居先の住所を秘匿している場合などの場合は、面会交流を拒否する理由となり得ます。
ただし、面会交流を拒否する合理的な理由を裁判所にわかってもらうためには、調停・審判での主張の内容や適切な証拠の確保などが重要となりますので、一度離婚問題に精通した弁護士へ相談されることをおすすめします。
他方、上述したように、同居親が別居親にたんに会いたくないだけであるという場合は、面会交流の実施に協力しない合理的な理由とまではされず、どのような工夫をすれば同居親と別居親が直接対面することとならずに面会交流を実施することができるのかという話し合いに進んでいくことが多いです。
5.面会交流の拒否には紛争がいつまでも続くリスクがある

子供をどうしても別居親に会わせたくない場合もあるものです。
ただ、親の子供に対する愛情は極めて深く、そして減衰していくことのないものです。
そのため、子供と会えない別居親は、絶対に引くことはないという前提に立って考える必要があります。
そして、裁判所が面会交流の拒否を認めるであろう事情(面会交流を拒否する正当な事情)が存在していない場合には、長期間面会交流を巡る別居親との間での紛争が継続した結果、結局、最終的には裁判所から面会交流の実施を認める審判が出されることとなる可能性が高いです。
審判が出されても面会交流に応じない場合には、別居親から改めて面会交流調停の申し立てがされたり、裁判所から履行勧告を受けたり、強制執行(間接強制)を受けたり、別居親から損害賠償請求訴訟が提起されたりする場合もあります。
つまり、面会交流が実施される状況に至るまで、延々と紛争が続いていく可能性があるということです。
他方において、感情的な問題のみならず、子供との新たな生活や、場合によっては再婚した後の生活などを考えなければなりませんし、子供が別居親と会うことを本当に嫌がっている場合には面会交流を実施しようにも実施できない場合もあります。
また、面会交流の実施にしっかりと協力していたとしても、別居親がさらに上乗せするように子供の生活状況を考慮していないとしか思えない無茶な面会条件を求めてきたりして、とてもじゃないが合意できない場合もあります。
このようにして、面会交流に関する話し合いは難航し、長期化してしまう可能性があるところです。
レイスター法律事務所では、無料相談において、
- 面会交流の拒否が認められる事情があるかどうか
- 面会交流に応じない場合には今後どのような紛争状況に至ることとなるのか
- 裁判所は審判でどのような判断をする可能性があるのか
- 具体的に今後相手との間でどのように面会交流に関する話し合いを進めていくことが最も良い方法か
などについて、具合的なアドバイスを行なっています。
無料相談のご予約は、こちらからお気軽にご連絡ください。