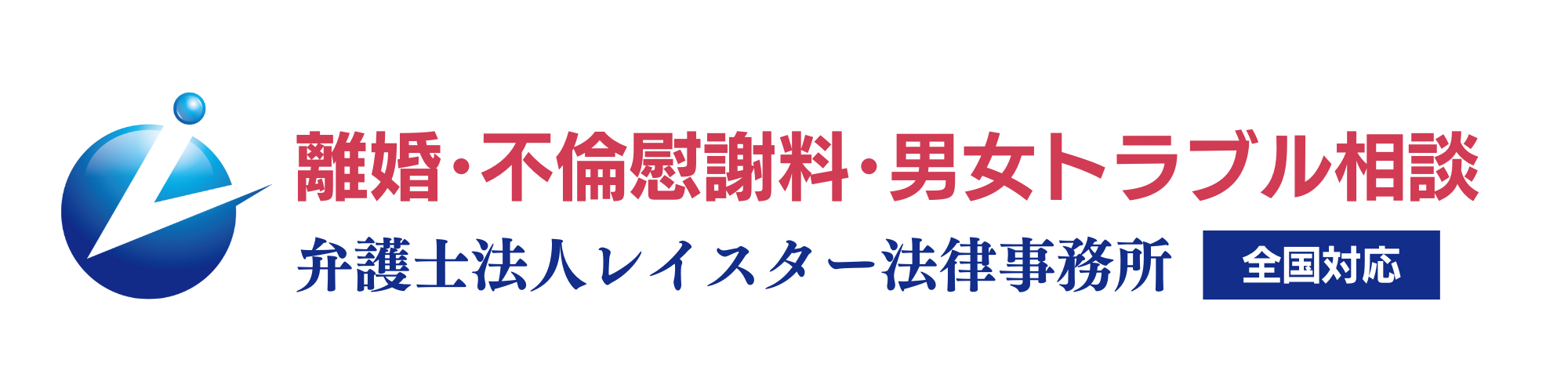よくある質問|離婚・不倫慰謝料・男女トラブル相談
FAQ よくある質問
FAQ MENU
FAQ
よくある質問
レイスター法律事務所について
-
法律相談の費用はいくらですか?
初回の法律相談は60分無料で実施していますので、相談料は発生しません。
なお、2回目以降の継続相談は、30分ごとに5,000円(税込5,500円)の相談料が発生いたします。
-
どんな内容でも無料で相談できますか?
当事務所の対応業務に関連するご相談であれば、基本的に全て無料でのご相談が可能です。
対応業務一覧(個人のお客様向け)
ただし、個別のご相談内容によっては、担当弁護士の判断によりご相談自体をお受けできない場合もございますので、ご了承ください。
-
土日や祝日の相談はやっていますか?
事前にご予約いただくことで土曜日の相談も可能です。
日曜・祝日の無料相談は現在実施していません。
ご相談予約は無料法律相談のお申込みフォームまたはお電話(03-5708-5846)にてお問い合わせください。
-
法律相談をした場合には依頼しなければならないのですか?
ご依頼いただくことは必須ではありません。
無料相談のみのご利用でも全く問題ございませんので、ご安心ください。
-
60分以上相談したいのですが、可能ですか?
無料相談は60分までとさせていただいております。
60分を超える場合には、30分ごとに5,000円(税込5,500円)の相談料が発生いたします。
なお、60分以上のご相談をご希望される際は、ご予約時にその旨をお知らせください
(事前にお知らせいただいていない場合は、担当弁護士の予定との関係で、ご相談を60分で打ち切らせていただく場合があります。)。
-
無料法律相談を受ける方法を教えてください。
当事務所では無料法律相談を完全個室で行なっており、予約制となります。
無料法律相談のお申込みフォームまたはお電話(03-5708-5846)にてお問い合わせください。
-
今からすぐに相談したいのですが可能ですか?
法律相談は完全予約制でのご案内となります。
相談室の使用予約の状況や担当弁護士の予定の状況により、当日のご相談をお受けできない場合がございます。
その場合には、最短で相談可能な日程をお伝えいたしますので、無料法律相談のお申込みフォーム又はお電話(03-5708-5846)にてお問い合わせください。
-
電話やメールでの法律相談は可能ですか?
当事務所では初回の法律相談はご来所またはオンラインでの実施のみとしており、お電話やメールでのご相談はお受けしていません。
※2回目以降の継続相談や、ご依頼後の打ち合わせはお電話でも実施しています。
-
子どもと一緒に相談に行って良いですか?
お子様と一緒にご来所いただくことも可能です。ご予約の際にお気軽にお申し付けください。
-
弁護士に相談するようなことかどうかが分からないのですが。
ご相談内容が弁護士に相談するような問題なのかどうかを心配されているご相談者もおられます。
ただ、弁護士に相談するような問題なのかどうかを一番正確に分かっているのは、その案件に習熟している弁護士です。弁護士法人レイスター法律事務所では、弁護士に相談するような問題なのかどうかについても含め、ご相談者の抱える問題を解決するために弁護士として何ができるのか、何ができないのかを丁寧にご説明しています。ご安心してなんでもご相談くださいませ。
-
弁護士に依頼する場合の費用はどれくらいかかりますか?
ご依頼の際の費用に関しては、こちらをご確認ください(費用はこちら)。
なお、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。
-
他の弁護士に依頼している場合でも、無料で相談できますか?
他の弁護士に依頼しており、セカンドオピニオンでのご相談の場合は無料相談の対応となりません。
初回より有料相談(30分ごとに5,500円)でのご案内となります。
-
友人や家族の問題についても無料で相談できますか?
ご相談者様が当事者ご本人様でない場合(親族や第三者の方からのご相談)は承っておりません。
財産分与に関するよくある質問
-
財産分与のときに住宅ローンやカーローンが残っている場合は?
離婚の際に、結婚後に購入した持ち家の住宅ローンや車のカーローンが残っていることは非常によくあるパターンです。
夫婦が婚姻期間中に負ったローンや借金は、財産分与の計算上、当該負債の名義人の他のプラス財産から差し引くことが認められます。
また、不動産ローンが不動産査定評価額よりも高額である場合(オーバーローン)には、他のプラス財産との損益通算的な処理が認められることが一般的です。なお、そのような損益通算的な処理をしたとしても、なお借金(負債)の方が上回っている場合もあります。しかし、そのような場合であっても、財産分与はあくまで資産を分与する制度ですので、当該借金(負債)の負担を他方配偶者と分けることは認められていません。
-
親族から相続した遺産も財産分与の対象になるの?
遺産などの夫婦が築いたものとはいえない財産は夫婦共有財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。
このような財産分与の対象とならない財産を「特有財産」といいます。
特有財産の典型例は、以下のものです。
①婚姻前から所有していた財産
②相続により取得した財産
③親から贈与を受けた財産
④上記①②③を原資として取得した財産
④の例としては、親から生前贈与を受けた500万円で購入した自動車などは特有財産となります。
このように特有財産は財産分与の対象となりませんが、調停や裁判ではその財産が特有財産に該当することを証拠に基づいて証明する必要があります。
-
結婚前から所持していた財産も財産分与の対象になる?
財産分与は、結婚してから獲得した財産を夫婦で分け合う制度であるため、婚姻前から所持していた財産は財産分与の対象から除外されます。
このような財産分与の対象とならない財産を「特有財産」といいます。
特有財産の典型例は、以下のものです。
①婚姻前から所有していた財産
②相続により取得した財産
③親から贈与を受けた財産
④上記①②③を原資として取得した財産
このように特有財産は財産分与の対象となりませんが、調停や裁判ではその財産が特有財産に該当することを証拠に基づいて証明する必要があります。
-
子供名義の預金や保険は財産分与の対象になるの?
子供名義の財産であっても、その原資が夫婦共有財産であった場合には、やはり夫婦共有財産として財産分与の対象となります。
夫の給与を子供名義の預金口座に入金して積み立てていた場合や、子供がもらったお年玉を子供名義の口座に貯めていた場合などがよくある例です。また、子供名義で契約している生命保険や学資保険なども財産分与の対象となります。なお、学資保険に関しては、離婚後に子供の親権を失う方の親の名義のままでは学資保険の本来の価値が発揮できませんので、離婚後に子供の親権者となる方の親に名義を書き換えて引き継がせるという財産分与の方法を取る場合もあります。
養育費に関するよくある質問
-
養育費を決めずに離婚した場合も後から請求できますか?
離婚の際に養育費に関する事項を取り決めていなかったとしても、離婚後に養育費を請求することは可能です。
ただし、養育費は、権利者が義務者に対して養育費を請求する意思を明確に示した時から具体的に支払う義務が発生するものと考えられています。そのため、養育費を請求したい方は、できる限り早期に相手に内容証明郵便で請求したり、養育費調停を申し立てたりする必要があります。
-
養育費を支払わずに強制執行されたらどうなる?
養育費の金額を公正証書や調停・審判・裁判で決めていたにも関わらず、決められた養育費の支払いをしなかった場合には、権利者(受け取る側)から強制執行を実施される可能性が高いです。強制執行されると、預金口座を差し押さえてそこから強制的に養育費の支払いがされたり、裁判所から勤務先に連絡が行き、給与を差し押さえられ、給与から直接養育費が引かれたりすることとなります。決められた養育費はきちんと支払いましょう。
-
養育費を受け取ったら税金はかかりますか?
子供の生活費・教育費の支払いは通常認められるものの範囲内であれば非課税とされるため、養育費は原則として課税されません。
ただし、将来にわたる養育費を一括払いで受け取った場合は、この「通常必要と認められるもの」を大幅に超えた金員を受け取っていることとなりますので、贈与税の課税対象とされてしまう可能性があります。
離婚慰謝料に関するよくある質問
-
離婚慰謝料は離婚した後も請求することができますか?
離婚慰謝料は、離婚した後も請求することができます。ただし、離婚した時から3年が経過している場合には時効消滅してしまいます(民法724条)。離婚後に離婚慰謝料請求を考えている方は、早めに行動に移しましょう。
-
離婚慰謝料が認められやすいケースは?
夫婦が離婚に至った原因が専ら相手の不倫・浮気である場合には、高確率で離婚慰謝料が認められます。また、相手からのDVやモラハラ、子供への虐待行為があった場合にも、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。(受け取る側)から強制執行を実施される可能性が高いです。
強制執行されると、預金口座を差し押さえてそこから強制的に養育費の支払いがされたり、裁判所から勤務先に連絡が行き、給与を差し押さえられ、給与から直接養育費が引かれたりすることとなります。決められた養育費はきちんと支払いましょう。
-
性格の不一致だけで離婚慰謝料は取れる?
慰謝料の請求が認められるかどうかは、夫婦の婚姻関係が破綻した原因次第で結論が異なります。 離婚となった理由が「性格の不一致」や「価値観の違い」のみであるといった場合には、慰謝料請求は一般的には困難でしょう。 ただし、その他複合的な事情によっては慰謝料請求が可能な場合もありますので、まずは弁護士へ相談されることをお勧めします。
-
離婚慰謝料は年収によって金額が変わるの?
受け取れる慰謝料の金額は、被った損害の大きさによって変動するものです。 自分よりも相手の収入が低いからといって離婚慰謝料を全く請求できないわけではなく、そして必ずしも相手の年収が高ければ高額の離婚慰謝料が受け取れるわけではありません。
-
離婚慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?
離婚慰謝料は、離婚による精神的な苦痛に対する損害賠償の意味を持つため、基本的に所得税や贈与税はかかりません。 ただし、慰謝料の費目や金額、受け取り方によっては税金がかかってしまう可能性もあるため、事前に税理士や弁護士に相談することをおすすめします。