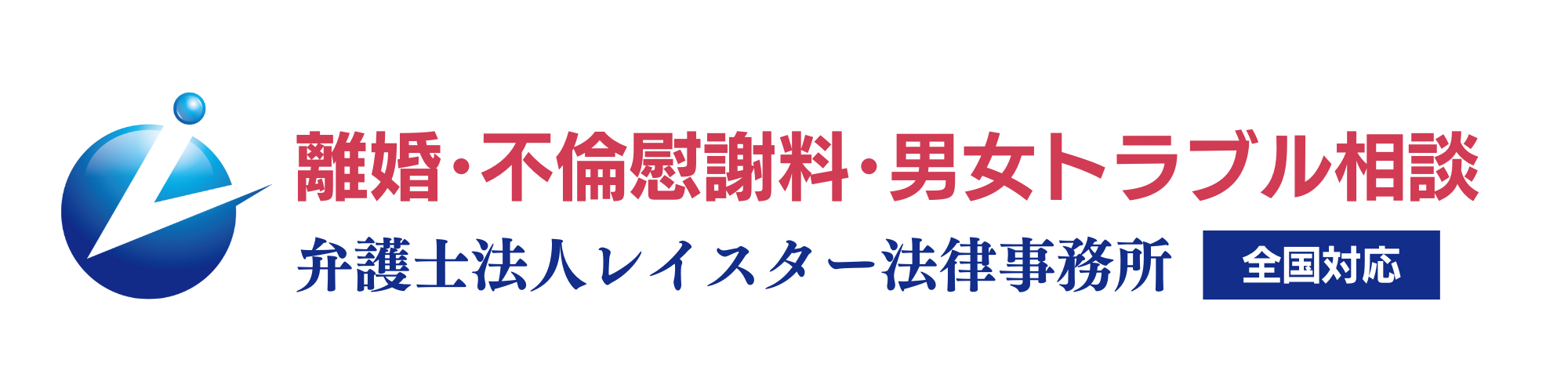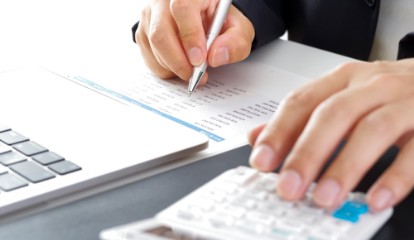離婚・不倫慰謝料・男女トラブル相談【全国対応】|弁護士法人レイスター法律事務所
離婚・不倫慰謝料
男女トラブル対応に特化
初回無料相談から親身になってアドバイス
来所・オンライン
60分無料
法律相談
離婚問題の
解決実績が
豊富な弁護士
ご自宅から
オンライン
相談OK
For WOMEN
妻側離婚・不倫のお悩み
女性の方
For MEN
夫側離婚・不倫のお悩み
男性の方
離婚・離婚後の基礎知識
MORE
FEATURE
レイスター法律事務所が
選ばれる理由
離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に
本当に強い弁護士がベストを尽くします
離婚問題や不倫(不貞)慰謝料問題、貞操権侵害などの男女トラブルは、人生そのものに多大な影響を及ぼし得る問題です。 離婚・不倫慰謝料・男女トラブルに精通し、多くの解決実績を有するこの分野に本当に強い弁護士が、一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、最善の解決結果を獲得するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

-

離婚・不倫問題・男女トラブルに
強い弁護士がベストを尽くす離婚・不倫慰謝料・男女トラブルに関する法的知識やトラブル解決のための交渉戦略に精通し、多くの解決実績を有するこの分野に本当に強い弁護士が、ご依頼者ひとりひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。
-

日常生活への影響を
最小限に抑える工夫感情的に対立している相手と直接会ったり直接連絡をしたりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。
-

依頼者ファーストで
スピーディーな対応当事務所では、スピーディーな解決のため、ご依頼の手続完了後、原則として翌営業日にはご依頼の案件対応を開始するというルールを徹底しています。その他、相手や裁判所から事務所に届いた書類は、原則として当日中(遅くとも翌営業日)にはご依頼者にご報告しており、リアルタイムで状況を把握いただくことが可能です。
CASES
解決事例
実際の解決事例を
ご紹介いたします。
離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。
-

年代:30代
職業:会社員
離婚手続き
不倫慰謝料
結婚歴:3〜5年
手続き:協議離婚
不貞をしてしまった有責配偶者である夫から離婚を請求し、協議離婚で早期に解決!
結果とポイント
別居から1年以上進展のなかった離婚問題でしたが、結果、当事務所にご相談にお見えになってから4か月で協議離婚が成立し、早期で離婚が成立することとなりました。
2025.06.28
-

年代:30代
職業:会社員
男女トラブル
主な争点:慰謝料
【婚約破棄】裁判を提起し、勝訴的和解成立で慰謝料100万円獲得!
結果とポイント
裁判を提起した当初、相手方は、婚約が成立していないとして慰謝料を払わないと反論していました。しかし、粘り強く裁判期日で主張・立証を重ね、最終的には和解となり、慰謝料100万円を獲得することができました。
2025.06.28
-

年代:40代
職業:会社員
離婚手続き
離婚前相談
結婚歴:5〜10年
離婚の原因:性格の不一致、相手のDV・モラハラ
手続き:協議→調停
早期に離婚を成立させ、対立していた面会交流の条件につき、双方とも納得のいく条件で合意!
結果とポイント
離婚調停は概ね半年程度で合意に至り、適正な財産分与を受け取ることができ、また、夫が自宅へ残した私物の処分に関しても、無事、解決しました。
また、離婚後に本格的な調停が開始された面会交流調停では、当事者の現在の生活や心情、子どもの年齢・性格に即した面会条件を詳細に詰めて合意することができました。
2025.06.28
-

年代:40代
職業:パート
離婚前相談
結婚歴:1年未満
主な争点:離婚するかどうか、その他
離婚の原因:性格の不一致等
手続き:離婚調停、婚姻費用分担請求調停
結婚相談所を通じて結婚した夫に個人情報を破棄させてスピード離婚した事例
2024.12.24
-

年代:30代
職業:会社員
離婚原因
離婚手続き
結婚歴:6~10年
主な争点:離婚するかどうか
離婚の原因:浮気・不倫
手続き:離婚協議→離婚調停
不倫した側からの離婚請求であったが妻を粘り強く説得して調停離婚が成立した事例
2024.12.24
-

年代:30代
職業:会社員
面会交流・親権
主な争点:面会交流の条件
手続き:面会交流調停
再婚・出産後に面会交流に協力しなくなった元妻との間で面会交流の再開・今後の協力の合意が成立した事例
2024.02.03
あなたの抱える不安や疑問に、
弁護士が寄り添い解決へ導きます
初回60分無料相談/中目黒駅徒歩8分/全国からオンライン相談受付中
For WOMEN
妻側離婚・不倫のお悩み
女性の方
ひとりで悩まず
弁護士にご相談ください
For MEN
夫側離婚・不倫のお悩み
男性の方
有利な離婚達成に向けて
弁護士へご相談ください
離婚・離婚後の基礎知識
MORE
FLOW
ご依頼までの流れ
無料相談からご依頼までの
流れをご説明します
初回無料相談のお問い合わせから、実際にご依頼いただくまでの流れは以下の通りです。
-
STEP
01
お問い合わせ
-
STEP
02
予約日程調整
-
STEP
03
来所/オンライン相談
-
STEP
04
契約
-
STEP
05
個別対応開始
-
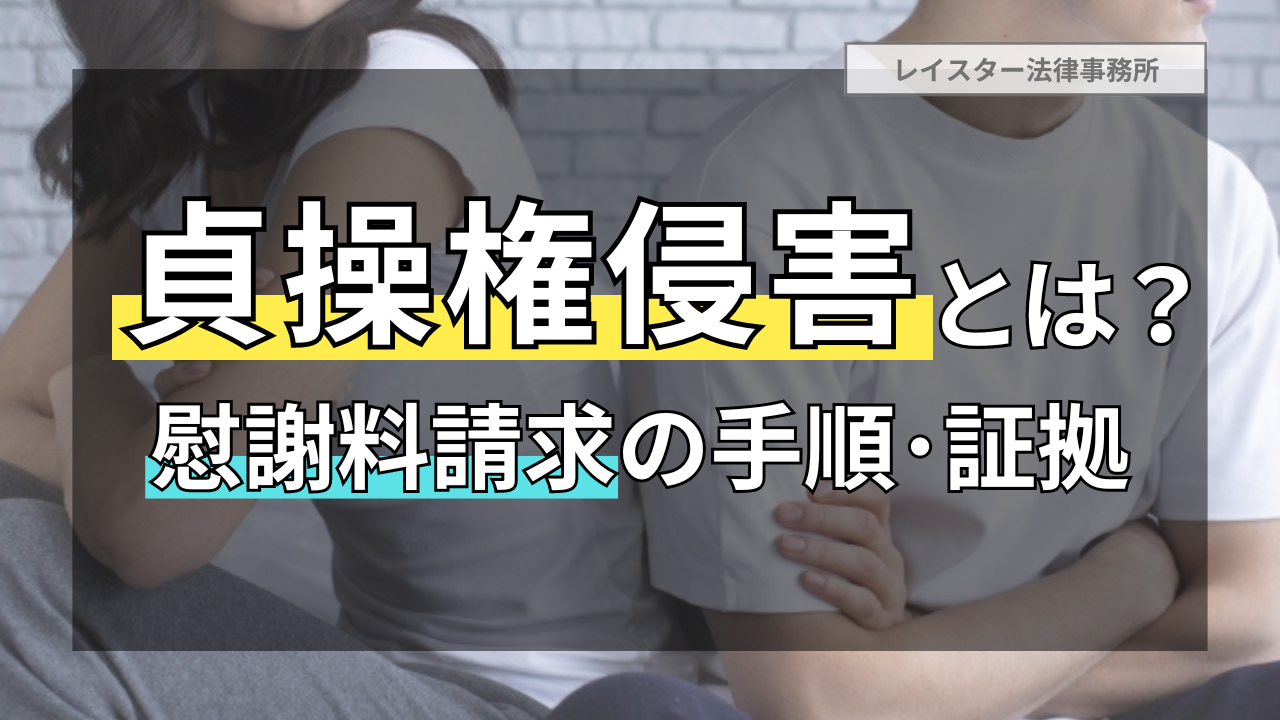
2024.10.10
男女トラブル
貞操権侵害とは?慰謝料請求の全手順と必要な証拠を詳説
2024.10.10
-
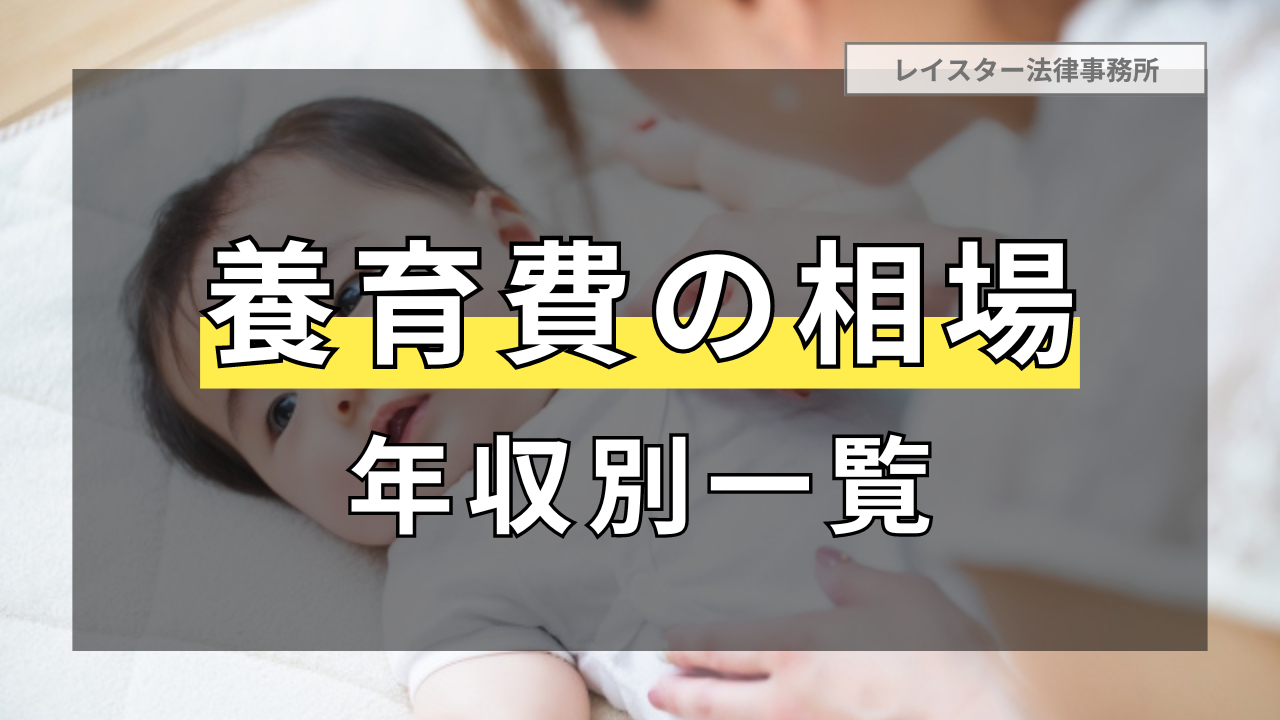
2024.08.09
養育費
養育費の相場金額の一覧!具体的な養育費の金額を年収別に解説【義務者の年収400万円〜2000万円まで】
2024.08.09
-
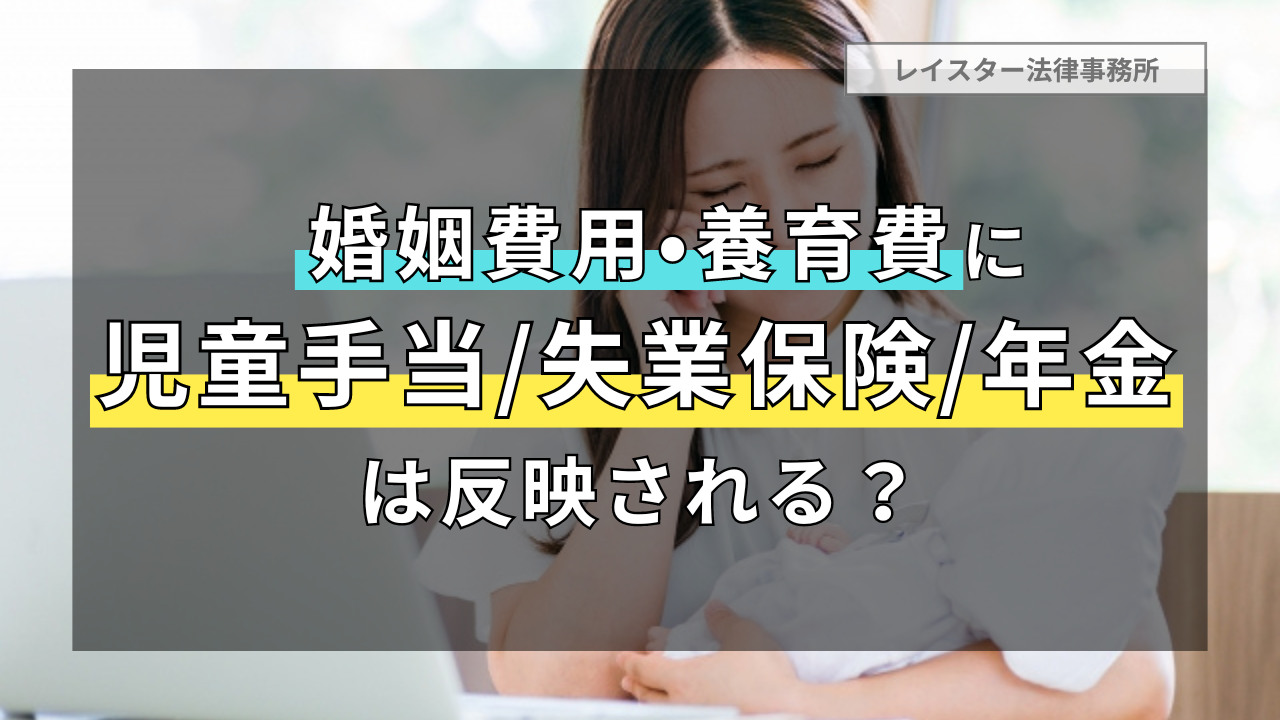
2022.08.05
婚姻費用
婚姻費用や養育費の金額に児童手当・失業保険・年金収入などは反映される?
2022.08.05
-
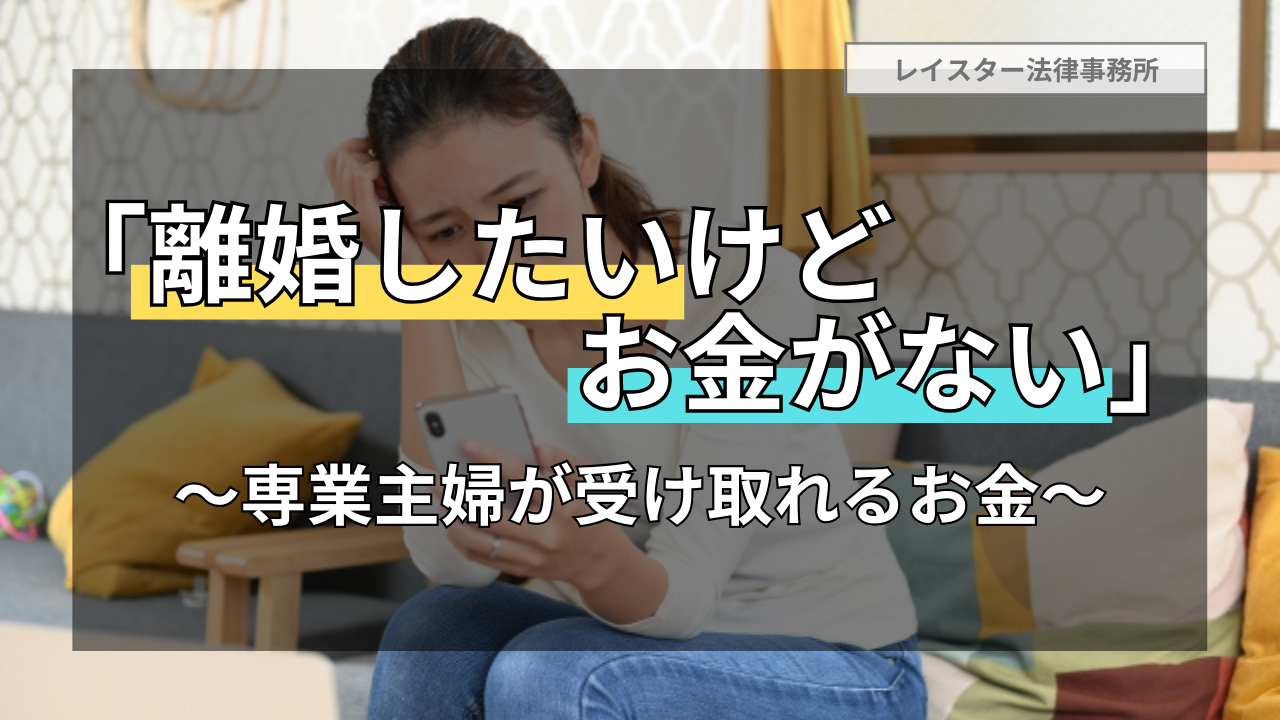
2022.07.06
離婚前相談
離婚したいけれどお金がない!専業主婦が受け取れる生活費などのお金について解説
2022.07.06
-
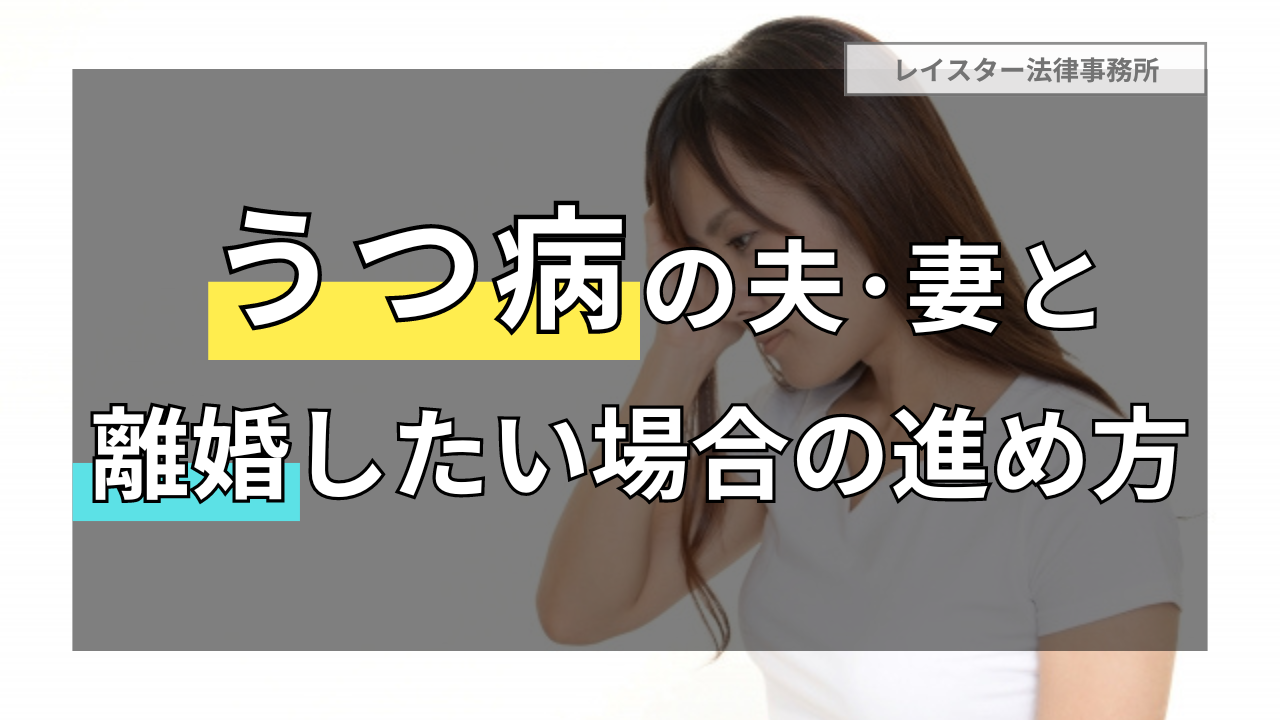
2022.06.27
離婚原因
うつ病の夫(妻)と離婚した方がいい場合と離婚したい場合の進め方
2022.06.27
-
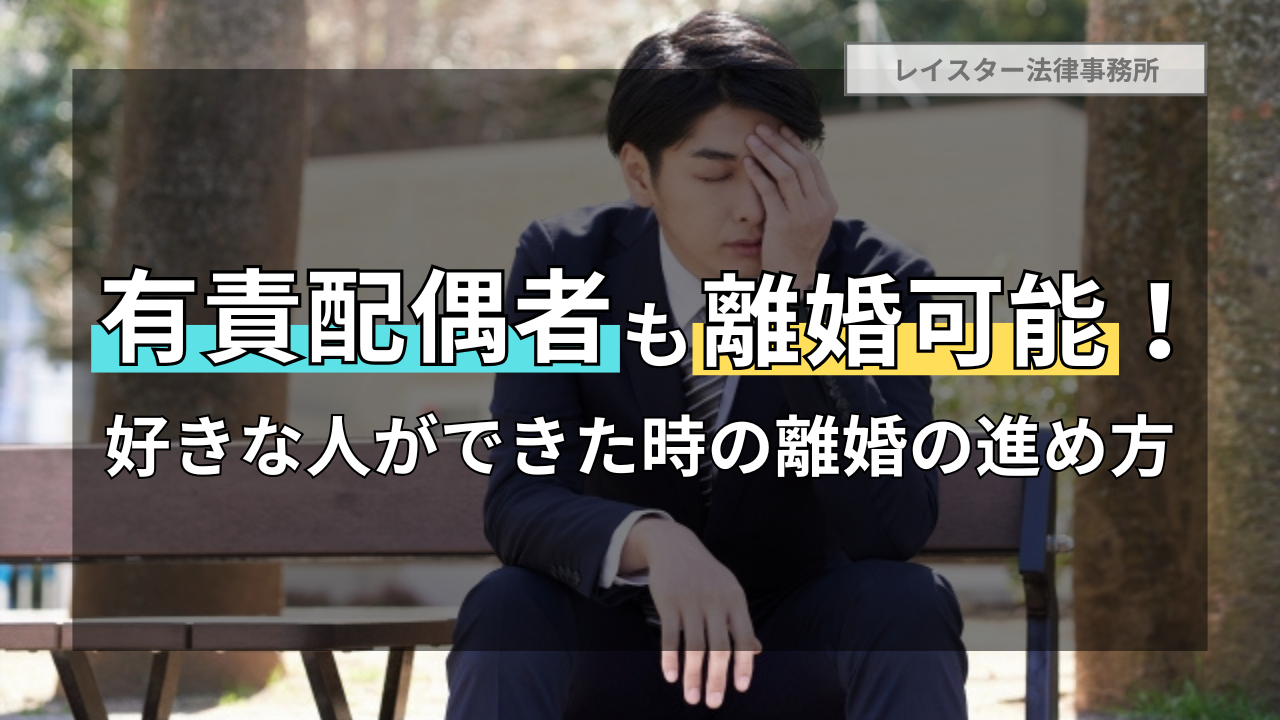
2022.06.17
離婚前相談
有責配偶者でも離婚は可能!好きな人ができた時の離婚までの進め方
2022.06.17