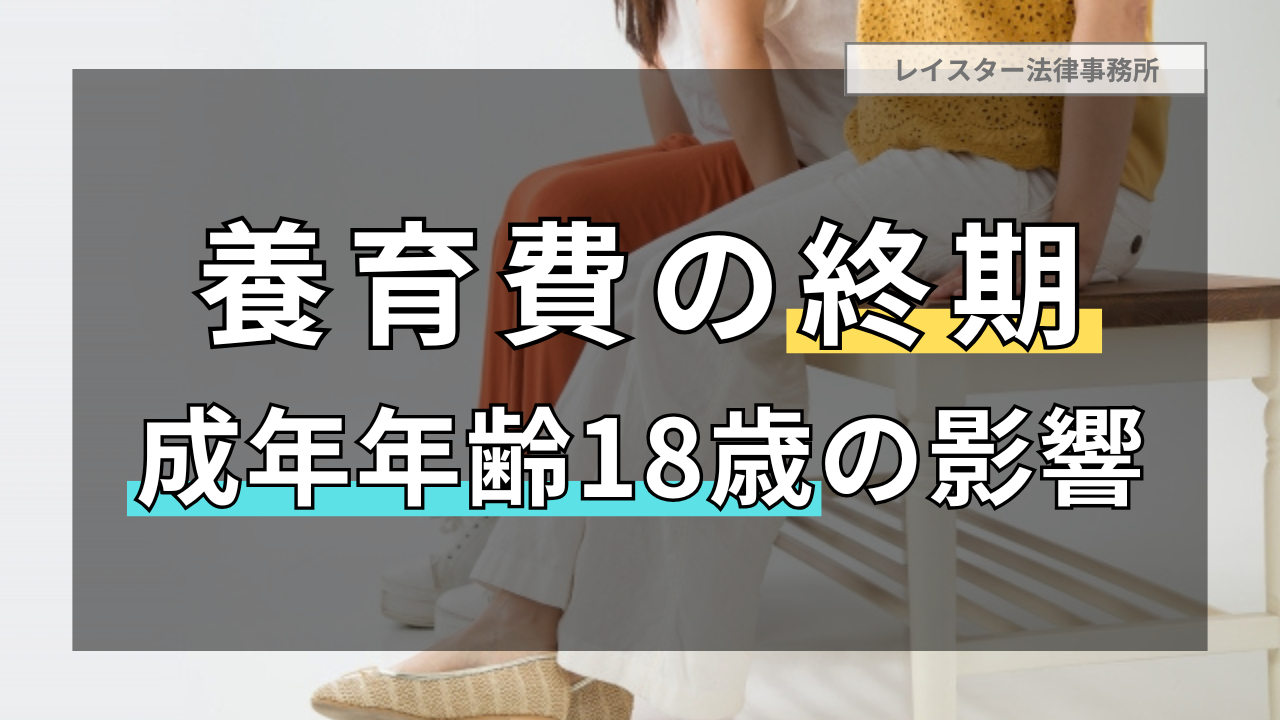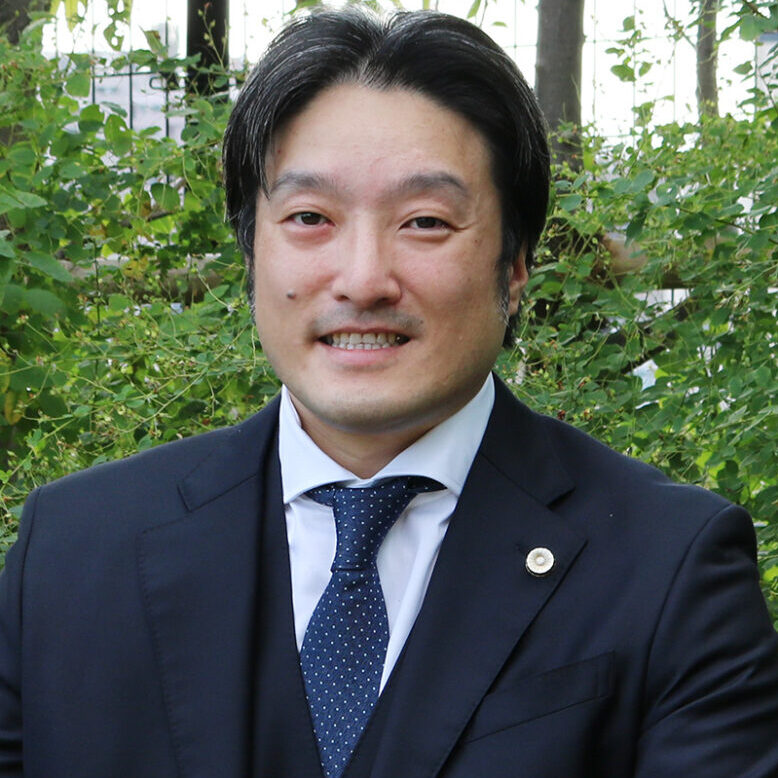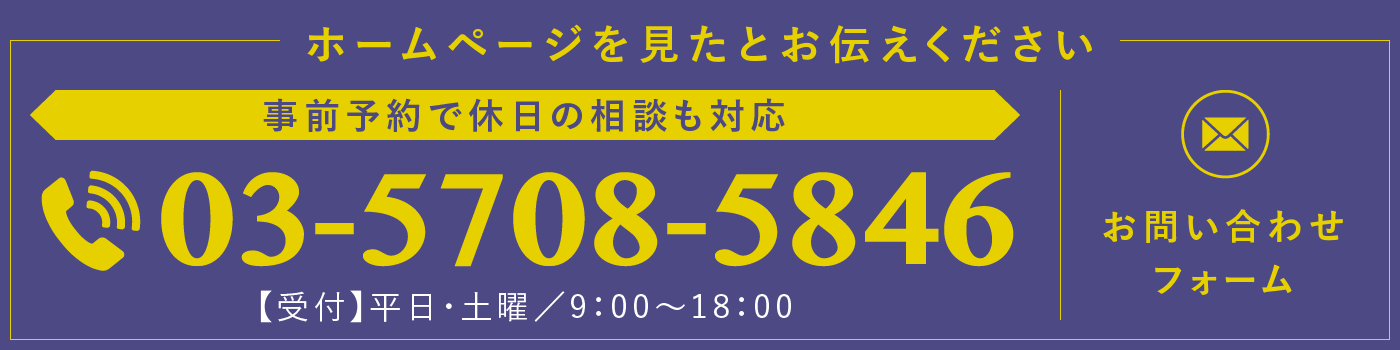法律改正で令和4年4月1日(2022年4月1日)から成年年齢が18歳に引き下げられました。
「18歳=成年」の社会となったことで、養育費の支払いも18歳までとなったのでしょうか。
この法律改正が養育費の終期に与える影響について、法務省が示した見解があります。
しかし、養育費の支払義務を判断するのは法務省ではなく、裁判所です。
今後、成年年齢が引き下げられたことが養育費の終期を巡る夫婦の話し合いにどのような影響を及ぼし得るかについて解説します。
このページの目次
1.法律改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた影響

民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
今後の社会は、「18歳=成年」という社会に変わったわけです。
これにより、養育費の終期はどのようになったのでしょうか。
2.法務省の見解
法務省は、成年年齢の引き下げの養育費への影響について、以下のように述べます。
法務省の見解(平成30年10月4日)
子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
法務省の意見のポイントをまとめますと、次のようになると思います。
ポイント①
既に「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取り決めがある場合は、従前通り「20歳まで」養育費の支払義務を負う。
ポイント②
養育費は未成熟子である間は発生するものであるから、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではない。
ポイント③
新たに養育費に関する取決めをする場合には、明確に支払期間の終期を定めることが望ましい。
3.法務省の見解のポイント①について
ポイント①
既に「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取り決めがある場合は、従前通り「20歳まで」養育費の支払義務を負う。
法務省は、既に「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取り決めがある場合は、従前通り「20歳まで」養育費の支払義務を負うと述べます。
しかし、養育費の支払義務を判断するのは法務省ではなく、裁判所です。
法務省が上記のように述べているからといって、裁判所がその通りの判断を示すことが決まったというものではありません。
今後、裁判所がどのような判断を示すのかは、今後明らかになっていくことでしょう。
アドバンスな交渉戦略①
「子が成年に達するまで」との取り決めがあった場合に、成年年齢の引き下げが養育費の終期に影響する(養育費の終期が18歳になる)と考えることもできます。
つまり、当事者間の養育費の終期の取り決め内容はあくまでも「子が成年に達するまで」のはずです。
法務省は、「取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったこと」を理由に、従前通り「20歳まで」養育費の支払義務を負うと述べています。
しかし、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる内容の法律改正が成立したのは平成30年6月13日です。
それが施行される(実際に成年年齢が18歳に引き下げられる)時期が令和4年4月1日からであることもこの時に決まっています。
この法律改正の存在を知らなかった人も多いでしょうが、知っていた人も多いはずです。
当然テレビのニュースでも繰り返し流れています。
離婚する前に夫婦間で会話をしていたかもしれません。
また、実際に離婚する際に養育費の終期を話し合って取り決めようとする際には、相応に様々調べたり検討したりしているでしょうし、弁護士から無料法律相談でアドバイスを受けていた可能性だってあります。
それにも関わらず、あえて「子が成年に達するまで」との養育費の終期の取り決めをしたのであれば、その夫婦は「子どもが成年に達する=18歳」と想定した上でそのように取り決めた可能性だってあるはずです。
また、社会一般として子どもが未成年者と扱われるような時期の間は養育費の負担をするが、社会一般として子どもが未成年者と扱われなくなった以上は養育費の負担はしないと考える人もいるでしょう。
そのような考え方が夫婦で共有されていた場合もあるでしょう。
そのために、養育費の終期について、子どもの年齢でズバッと決めるのではなく、あえて「成年に達するまで」と取り決めていることもあり得る話です。
そのような夫婦にとっては、子どもが法律で18歳から成年とされるようになったのであれば、養育費だって18歳までで打ち切りとなることが想定されていたと言えるかもしれません。
このように考えると、法務省の見解が絶対の正解とは言えないはずです。
この点は、今後、多くの主張反論が繰り広げられ、最終的には裁判所の判断が示されていくものと思われます。
4.法務省の見解のポイント②について
ポイント②
養育費は未成熟子である間は発生するものであるから、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではない。

法務省は、養育費は未成熟子である間は発生するものであるから、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではないと述べます。
養育費を支払わなければならい理由は、離婚した後も実の子どもに対する扶養義務を負っているからです(民法877条1項)。
そのため、養育費は、子どもが扶養してあげなければ生活できない状態にあるうち(子どもが「未成熟子」である間)は支払ってあげなければならないと考えられています。
つまり、そもそも養育費は子どもが「未成熟子」である間は発生するものです。
そして、「未成熟子」とは、一般的に、未だ成熟化の過程にあって、労働に従事すれば心身の発育を害される恐れがあるために、他者による扶養を必要とするような期間にある子どもをいいます。
成年年齢が18歳になったことで18歳になれば当然に「未成熟子」でなくなることになったというものではない、ということは、いわば当然のことでしょう。
そのため、「成年年齢の引き下げによって子どもが成年になったから養育費を打ち切りたい!」という主張は通らないと考えられます。
アドバンスな交渉戦略②
養育費の終期は、家庭裁判実務上、「20歳まで」と定められることが通例となっています。
なぜ「20歳まで」と定めることが通例となっているかを考えると、その背景には、未成年者である間は養育費を支払いましょうという考えがあると思われます。
しかし、令和4年4月1日からは、子どもは18歳で成年になります。
今後の社会は、「18歳=成年」という社会に変わったわけです。
そうだとすれば、特に高校卒業で就職する場合は、社会的な風潮として、「未成年者(18歳になるまで)は親はちゃんと子どもの面倒を見なければならないでしょうが、もう成年になった(18歳になった)のだから、一人前の大人として生きていかなければならないよ」というような風潮が出てくる可能性もあるでしょう。
そのため、養育費の終期の取り決め方に関しても、以下のような子どもが高校卒業後に就職することを見越した内容とすることが、家庭裁判実務上も徐々に一般的になっていく可能性もあります。
子どもが高校卒業後に就職することを見越した合意内容
養育費の終期を「未成年者が高等学校を卒業した後に就職する場合には未成年者が高等学校を卒業する月までとし、未成年者が高等学校を卒業した後に大学に進学する場合には未成年者が満22歳に達した後の最初の3月までとする」
5.法務省の見解のポイント③について
ポイント③
新たに養育費に関する取決めをする場合には、明確に支払期間の終期を定めることが望ましい。

法務省は、新たに養育費に関する取決めをする場合には、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと述べます。
これはその通りです。
養育費は、離婚後の子どもの生活状況に直結するものであり、極めて重要です。
しかし、離婚後は、養育費の支払義務者は、子どもの親権を失いますし、子どもと一緒に生活をしている状況ではなくなります。
離婚してから期間が経過すればするほど、人生の必須のパーツとして新たな恋人、新たな配偶者(再婚相手)、新たな子どもが現れ、その分自身の生活の構成要素になっていない子どもに対する興味・関心は薄れていきます。
相手がどうにかして養育費という経済的な負担を軽減できないものかと日々考えるようになる可能性も十分に想定できます。
そのような状況でも、取り決めた養育費はしっかりと最後まで支払ってもらわなければなりません。
離婚後のトラブル防止のため、支払期限だけではなく、養育費に関する事項は全て明確に取り決めておくことを強くお勧めします。
6.子どものためにも養育費はしっかりと請求しよう!
養育費の支払いは毎月受けられるものであり、その総額は相当高額になります。
子どものためにも、養育費は確実に支払ってもらうことが良いでしょう。
ただ、上述したように、法律改正で成年年齢が18歳になった影響については、未だ家庭裁判実務上の取り扱いなどが決まっておらず、今後家庭裁判所では様々な主張が繰り広げられていくところでしょう。
養育費の金額が月額1万円違うだけで、1年で12万円、10年では120万円もの違いとなります。
できるだけ有利な養育費の請求を成功させるためにも、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
レイスター法律事務所では、無料法律相談において、想定される養育費の具体的な金額や、少しでも有利な金額となるような話し合いの進め方などを詳細にお伝えしています。
養育費や離婚問題でお悩みの方は、是非、こちらからお気軽にご連絡ください。