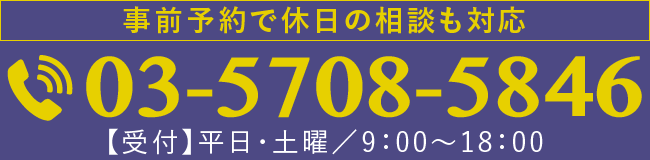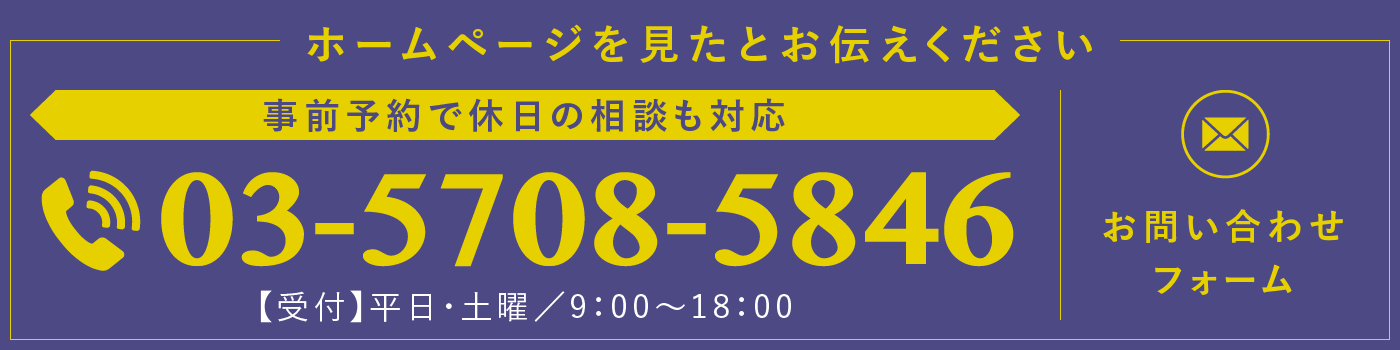コラム
貞操権侵害とは?慰謝料請求の全手順と必要な証拠を詳説
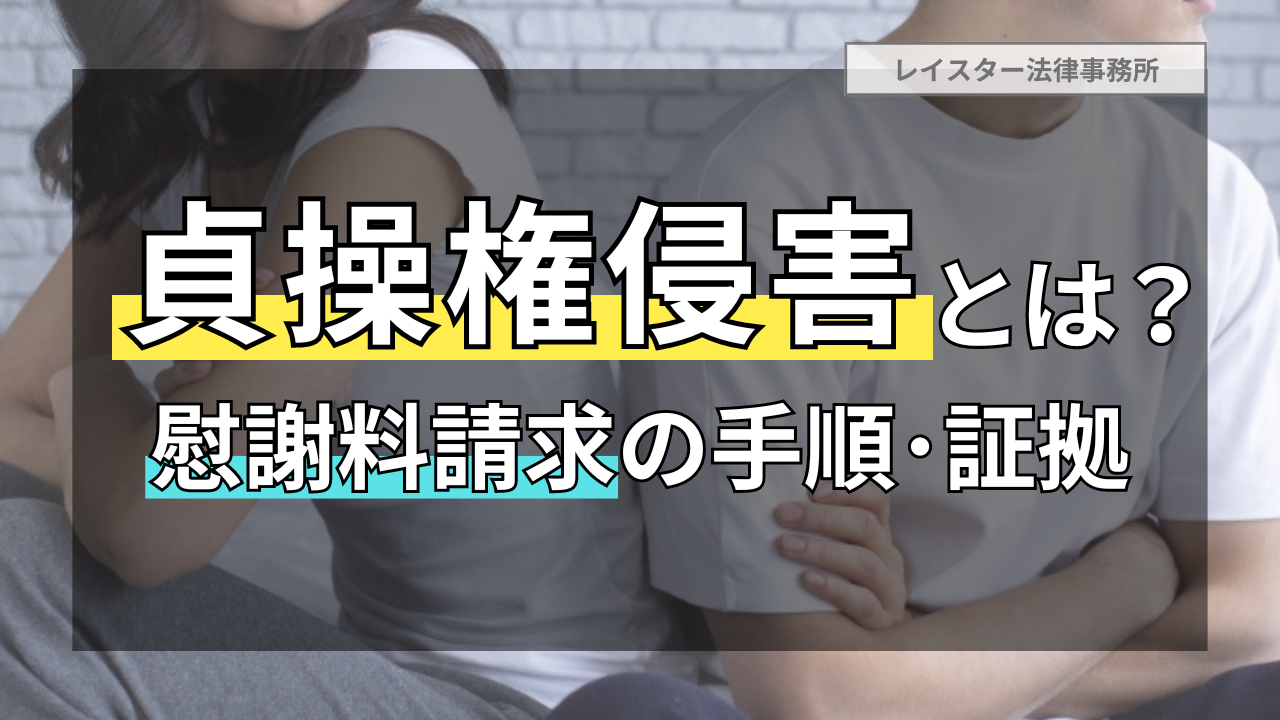
養育費の相場金額の一覧!具体的な養育費の金額を年収別に解説【義務者の年収400万円〜2000万円まで】
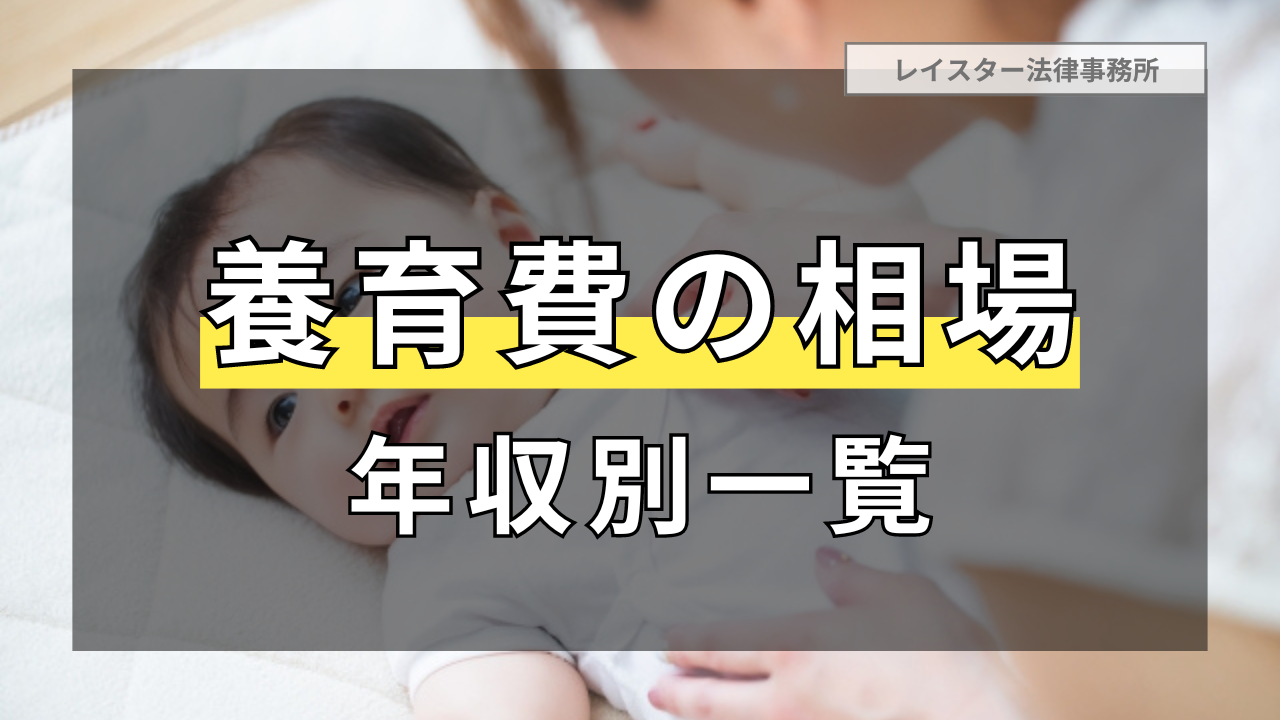
有利な財産分与を勝ち取るために!財産分与の「財産」以外の考慮要素を解説
財産分与は、夫婦共有「財産」を離婚時に分け合う制度ですが、実は、このように「財産」に着目した財産分与は、数種類ある財産分与のうちの①「精算的財産分与」のことを指しています。
そして、財産分与には、①「精算的財産分与」の他にも、②離婚後の扶養を考慮する「扶養的財産分与」、③離婚に伴う慰謝料を考慮する「慰謝料的財産分与」、④婚姻費用の分担の状況を考慮する「過去の婚姻費用の精算」があります。
このような多様な財産分与の中に、財産分与の話し合いを有利に進めるヒント・きっかけが隠されている可能性があります。
【この記事を読む】【婚姻費用】相手が無職・低収入の場合は潜在的稼働能力を主張しよう
婚姻費用は別居中の生活費であり、生活を維持していく上で極めて重要な費用ですので、別居をしたら婚姻費用分担請求を忘れずに。
婚姻費用の金額は夫婦の収入金額に基づいて計算されるのが原則です。
ただし、現実の収入金額を前提として計算すると不当になる場合もあります。
その場合は、婚姻費用の金額を、現実の収入金額を前提とするのではなく、その気になれば稼げるであろう水準の収入(潜在的稼働能力)に基づいて計算をすることとなる場合もあります。
【この記事を読む】モラハラとは?モラハラ夫(妻)の特徴や具体的な言動と対処法
モラハラ(モラルハラスメント)とは精神的虐待(精神的暴力)のことを言います。
夫婦間のモラハラは、モラハラ被害者に逃げ場がなく、精神疾患などの深刻な被害が生じかねないものです。
モラハラ人間の大きな特徴の一つに「自分は相手よりも上・相手は自分よりも下」という精神性があり、そこから様々なモラハラ行動が引き起こされます。
モラハラ夫(妻)の一般的な特徴、具体的なモラハラ行動、モラハラ被害者が陥りがちな状況を解説します。
【この記事を読む】【養育費の終期】法律改正で成年年齢が18歳になった影響を解説
法律改正で令和4年4月1日(2022年4月1日)から成年年齢が18歳に引き下げられました。
「18歳=成年」の社会となったことで、養育費の支払いも18歳までとなったのでしょうか。
この法律改正が養育費の終期に与える影響について、法務省が示した見解があります。
しかし、養育費の支払義務を判断するのは法務省ではなく、裁判所です。
今後、成年年齢が引き下げられたことが養育費の終期を巡る夫婦の話し合いにどのような影響を及ぼし得るかについて解説します。
【この記事を読む】財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」とは?
離婚時の財産分与の割合は、家庭裁判実務上、「2分の1」が大原則です(「2分の1ルール」)。
自宅や自動車、預金・貯金、生命保険・学資保険、株式・有価証券、家具家電などの動産類、退職金や確定拠出年金なども全て「2分の1」。
高収入の人も専業主婦も「2分の1」です。
この「2分の1ルール」の理由や例外、メリットとデメリットを解説します。
【この記事を読む】夫の風俗通いが発覚!離婚・慰謝料請求は認められる?
夫が風俗に通っていたことが発覚した場合、今後の夫との婚姻関係をどうするか考えなければなりません。
夫を信じて婚姻関係を続けることとするか、夫との離婚を決意するかは、夫の態度やあなたの気持ち次第でしょう。
あなたが夫との離婚を決意した場合には、夫が風俗嬢とした行為が「不貞」に該当するかどうかで、離婚問題の進め方や慰謝料に関する事情が変わってきます。
【この記事を読む】パパ活とは?夫がパパ活をしていた場合の慰謝料請求と離婚問題を解説
「パパ活」とは、一般に、女性が男性と一緒の時間を過ごし、その対価を得る活動のことを言います。
夫がパパ活を利用し、対価を支払って女性とデートしていたことは、妻にとっては許しがたいものでしょう。
夫が妻に隠れてパパ活を利用することは妻の信頼を裏切る行為であり、夫婦の婚姻関係の破綻につながるものであって、離婚問題が持ち上がる十分な理由になるものですし、不倫慰謝料請求ができる場合もあります。
この記事では、そんな隠れパパ活夫に対する慰謝料請求と離婚問題について解説します。
【この記事を読む】認知とは?結婚していない父親から養育費をもらうための手続きを解説
不倫関係にある男性や内縁関係にある男性との間でできた子どもは、その男性(生物学上の父親)に扶養してもらって然るべき子どもです。
ただ、その男性に、子どもに対する法律上の扶養義務を負ってもらうためには、その男性と子どもとの間で法律上の親子関係を発生させる必要があります。
そのための手段が「認知」です。
父親が認知することを拒否したとしても、強制的に認知させた上、父親に対して養育費を請求することが可能です。
自分の子どもでありながら責任を負いたくないなどといった都合の良い甘えは通じません。
この記事では、認知を行う必要がある場合や認知により生じる権利・義務及び認知の種類や認知の方法について解説しています。
【この記事を読む】 « Older Entries