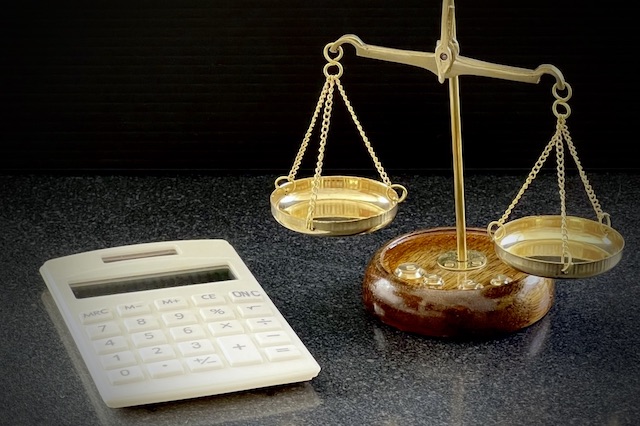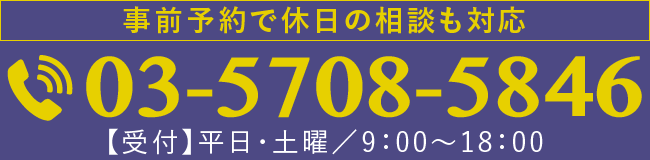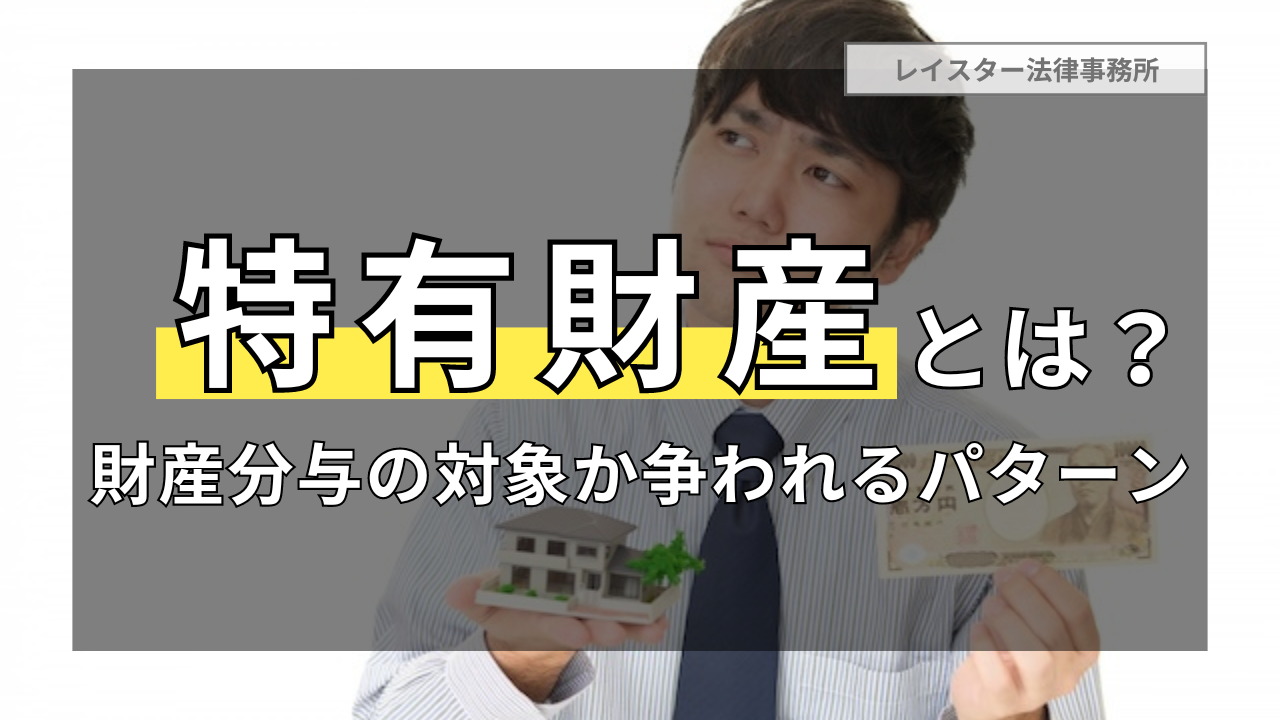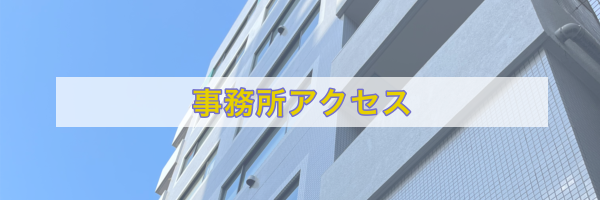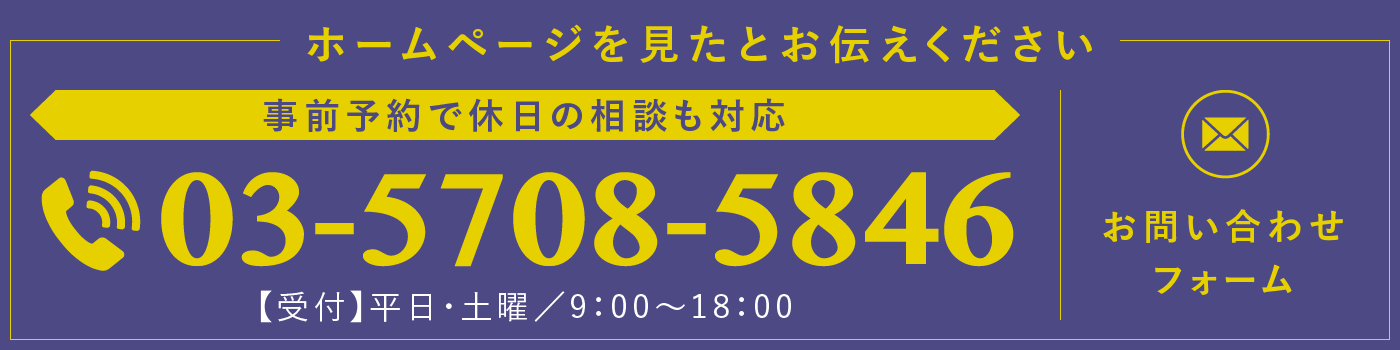特有財産(独身時代に形成した財産、相続した財産など)は財産分与の対象とならないのが原則です。
ただ、特有財産性を巡る話し合いには一筋縄ではいかない多くの問題が含まれています。
例えば、特有財産を原資の一部に用いて得た別の財産は財産分与の対象となるでしょうか。
また、特有財産と夫婦共有財産が混ざり合って渾然一体となっている預貯金は財産分与の対象となるでしょうか。
さらに、お小遣いをコツコツ貯めて築いた預貯金は、離婚の際に相手に分与しなければならないのでしょうか。
このページの目次
1.特有財産は財産分与の対象外となる

離婚時の財産分与では、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、基準時(別居時又は離婚時のいずれか早い時点)の換価価値(金額)で分け合います。
財産分与の割合は、よほどの特殊な事情がない限り2分の1となります (2分の1ルール)。
つまり、夫婦は、婚姻期間中の収入の金額に違いがあったとしても、離婚の際に、財産分与として、夫婦共有財産(夫婦が婚姻後に得た財産など)を各々2分の1ずつ保有している状況になるように分け合うこととなります。
夫婦共有財産とは、例えば、結婚後に夫婦のいずれか一方の名義で購入した財産(例:妻名義の車、夫名義の持ち家、子どものために加入した学資保険など)や、原資が夫婦のいずれかが結婚後に築いた財産であるもの(例:子ども名義の預貯金など)などのことを言います。
また、財産分与の計算は、通常、以下の流れで進みます。
- 財産分与の基準時(いつの時点の財産を分け合うのか)を具体的に確定する。
- 財産分与の基準時における夫婦それぞれの名義財産(夫婦共有財産)の総額を資料に基づいて明らかにする。
- 財産分与の基準時における夫婦それぞれの名義財産から夫婦ぞれぞれの「特有財産」を差し引く。
このように、「特有財産」に該当する部分の財産は、財産分与の計算の際に差し引くことが認められます。
2.特有財産とは?
⑴特有財産の典型例
財産分与は、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された財産を、離婚の際に公平に分け合う制度です。
そうだとすれば、名実ともに相手の協力とは完全に無関係に得た財産であれば、その財産は相手と分け合う必要はないはずです。
この名実ともに相手の協力とは完全に無関係に得た財産のことを、「特有財産」と言います。
例えば、以下の3つの財産はいずれも相手の協力とは完全に無関係に得た財産ですので、財産の種類(預貯金、不動産、自動車、保険、退職金、株式・国債などの有価証券、家具家電類など)を問わず、「特有財産」に該当するのが原則です。
「特有財産」の典型例
- 独身時代に形成した財産
- 相続した財産
- 親族等から贈与された財産
独身時代に購入した自動車や、独身時代に契約した保険の一部、独身時代から勤務している会社の退職金の一部などは、特有財産に該当します。
3.特有財産を原資として獲得した別の財産
⑴「特有財産」が姿を変えた別の物も財産分与の対象とならない

「特有財産」を原資(元手)として別の財産を得た場合、その別の財産は財産分与の対象とはなりません。
例えば、親から自動車を買い与えてもらった場合は、その自動車は特有財産ですので、財産分与の対象とはなりません。
それと同じように、親から贈与された100万円で購入した自動車も、財産分与の対象とはなりません。
さらに、別の物を取得するための対価の一部に「特有財産」が用いられていた場合は、その「特有財産」が用いられた分の価値は、財産分与の対象とならないと考えられています。
具体例で説明①
・自宅の購入に際して親から頭金を出してもらっていた場合
・親からの相続財産でローンの繰上げ返済をした場合
↓
親から出してもらった頭金や相続財産で住宅ローンの返済をした分は財産分与の対象とならない
なお、この場合の具体的な計算方法は、別途の機会に詳細に解説する予定です。
相続財産が離婚時の財産分与の対象となる例外的な場合を解説します
⑵特有財産が存在しているために格安で取得できた別の財産の取り扱い
「特有財産」が存在しているために、別の財産を格安で取得できる場合があります。
例えば、以下のような場合です。
夫が、親から、相続により、親の所有する建物とその建物が立っている土地の借地権を得た。
その後、夫は、その土地の地主と話し合って、地主からその土地の所有権を相場金額の4割という格安の金額で購入した。
なお、その際の土地の購入資金は、全額婚姻後の夫の給与を貯蓄した預金から出した。
この場合、当該土地の所有権を得るための購入資金は、全額婚姻後の夫の給与を貯蓄した預金です。
そのため、当該土地の取得の原資に特有財産は混入していないことから、当該土地は一から十まで全て夫婦共有財産であるようにも見えます。
そう考えた場合は、当該土地の査定評価額の全額が財産分与の対象となります。
しかしながら、夫が当該土地を相場金額の4割という極めて格安の金額で購入することができたのは、夫が当該土地の借地権を有していたからです(なお、一般に、借地権の価値は所有権の6割程度と計算される例が多いです。)。
つまり、夫は、当該土地の購入時に、既に借地権という当該土地の価値の6割程度の価値を有していたと言えます。
他方において、地主は「借地権が設定されている土地の所有権」という所有権の価値全体の4割程度の価値を有していたに過ぎません。
そのため、夫は、その地主が有していた4割程度の価値分の金員の負担で、当該土地の所有権を獲得することができたのです。
そして、当該土地の借地権は夫が親から相続により得た財産ですので、夫の特有財産です。
つまり、夫が当該土地を4割という格安の値段で取得できたのは、当該土地の価値の6割分は特有財産が負担してくれたためだと考えることができます。
このような状況ですので、夫は、当該土地の財産分与に際して、財産分与の対象となるのは当該土地の査定評価額の4割に過ぎない(当該土地の取得価格の6割は特有財産が原資となっているため差し引くべきである)などと主張することができると考えられます。
4.特有財産を含む預貯金の財産分与
⑴基準時の預貯金の中に特有財産がなおも存在しているといえるか

- 婚姻後に預貯金が減少・消滅していた場合
基準時の預貯金の中に独身時代に形成した金員や親から贈与・相続を受けた金員が存在していた場合は、当該金員は特有財産ですので、財産分与の金額の計算上、基準時の預貯金の金額から差し引くことができるはずです。
例えば、婚姻した時点で独身時代からの預貯金が200万円存在していたとします。
そして、別居の時点では預貯金は300万円ありました。
そうだとすれば、財産分与の対象となる金額は、別居の時点での夫名義の預貯金の金額300万円から婚姻した時点での夫名義の預貯金の金額200万円を差し引いた金額(300万円−200万円=100万円)であるように思えます。
しかし、本当にそういえるかどうかは、実は、婚姻開始から別居の時点までの全ての出入金履歴を見なければ分からないはずです。
このことについて、具体例で説明します。
具体例で説明②
⚫︎事例
夫は、婚姻時に、独身時代からコツコツと溜めていた預貯金200万円を有していた。
そして、妻と結婚した後も、その預貯金が入っている口座を別に分けることはせず、そのまま生活資金の口座として使っていた。
夫婦は子どもが生まれた際に、妻が育児休業を取得して稼ぎが少なくなったことから、生活資金が底をつき、一部借入れをして妻が復職するまでの急場を凌いだ。
その後、妻が復職して、家計が健全化し、徐々に貯蓄する余裕も生まれた。
ただ、夫が妻の妊娠中に職場の同僚の女性と不倫していたことが発覚し、それが原因で夫婦関係が破綻し、別居して離婚することとなった。
そして、別居の時点では、夫の預貯金口座には300万円の預貯金が存在していた。
⚫︎解説
確かに、夫は独身時代に形成した預貯金200万円を有していました。
しかし、その200万円は、一旦底をつき、全て消費してしまっています。
その結果、別居の時点で夫の預貯金口座に存在していた300万円は、その全額が婚姻開始以降に貯蓄された預貯金になっています。
つまり、この別居時の夫の預貯金300万円の中に夫が独身時代の貯蓄は1円も含まれていません。
そのため、この別居時の夫の預貯金300万円は、全額が夫婦共有財産であって、財産分与の対象となります。
具体例で説明③
上記の具体例とは少々事例を変えて、
・夫の預貯金の残高が婚姻開始後に一旦100万円まで減少したものの、
・別居の時点まで100万円以下にはなったことがなかった
とします。
その場合は、その残っていた100万円は、原則として夫の特有財産ということができそうです(ただし、下記の「独身時代から利用していた口座をそのまま婚姻後も継続して利用し続けていた場合」には、注意)。
このように、厳密には婚姻時から別居開始時までの全履歴を確認しなければ特有財産性は正確に算定できないということになります。
そのため、預貯金の特有財産性を巡る話し合いは、概ね以下の3パターンに分かれます。
- パターン1
基準時の残高のみで財産分与の計算をするパターン
- パターン2
基準時の残高から婚姻時の残高を差し引いて財産分与の計算をするパターン
- パターン3
基準時の残高から婚姻時の残高を差し引いた計算だけでは当事者が納得せず、婚姻期間中の取引履歴などを精査して財産分与の計算をすることとなるパターン
アドバンスな交渉戦略
金額的にはパターン3が最も有利になりそうだったとしても、パターン3の話し合いが最も離婚紛争が長期化します。
感覚的にはパターン3が自身に有利な計算となると感じていたとしても、それを正確に計算したり、相手が合意せざるを得ない状況を作ったりするためには、相手の預貯金の残高や婚姻時から別居時までの間の取引履歴などの立証資料が必要となる場合も多いです。
こちらが相手に対して「婚姻時から別居時までの取引履歴を全て開示せよ!」と要求しても、相手がそれに応じなければ、相手と交渉したり、相手を説得したりする必要があります。
それでも相手がどうしても取引履歴を提出しなければ、裁判所に調査嘱託を申し立てて、裁判所に取得してもらうことを検討する必要も出てきます。
しかしながら、裁判所が調査嘱託を実施してくれるかどうかは、担当裁判官の裁量的な判断であり、実施してくれないこともあります。
そうこうしているうちに、離婚の話し合いや、調停や裁判の手続きはどんどん長引いていきます。
どのパターンでどの程度相手の財産を追求していくかは、当事者双方がそれぞれ抱えている事情やそれにより受けられる見込み金額の多寡などの事情を踏まえて、何が自分にとって最もメリットとなる進め方かを検討する必要があるでしょう。
なお、実際の離婚の交渉・離婚調停では、パターン1やパターン2で当事者間の合意が成立する例が多い印象です。
- 独身時代から利用していた口座をそのまま婚姻後も継続して利用し続けていた場合
独身時代からの預貯金の金額が別居時まで維持されていた場合は、財産分与の金額の計算上、婚姻時の預貯金の金額を基準時の預貯金の金額から差し引くことができるはずです。
しかし、独身時代から利用していた口座をそのまま婚姻後も継続して利用し続けていた場合は、その口座に婚姻後も預金が入ったり出たりと繰り返されていくこととなります。
それが生活資金の口座などであった場合には、預貯金の出入りも頻繁に行われることとなります。
その場合は、預貯金が色付けされている訳ではありませんので、当該口座には独身時代からの預貯金と婚姻後に入金された預貯金が渾然一体となっている状況になります。
そのため、特に婚姻期間が長い場合は、家庭裁判所は、もはや基準時の預貯金が夫婦のいずれに属するのかは明らかではないとして、預貯金の特有財産性を認めてくれない(夫婦共有財産と扱われる)場合があります(民法762条2項)。
民法762条2項
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
つまり、この場合は、裁判所が、独身時代からの預貯金の特有財産性を認めてくれる場合と認めてくれない場合があるということです。
イメージで説明
イメージとしては、継ぎ足しを繰り返して利用している秘伝のソースの壺です。
壺が口座を表し、秘伝のソースが預貯金を表します。
例えば、2010年には、壺に10Lの秘伝のソースが入っていたとします。
そして、毎日秘伝のソースを壺から一部取り出して使っては、新たに秘伝のソースを作って継ぎ足していたとします。
そうすると、10年経過した2020年の時点でその壺に入っている10Lの秘伝のソースは、10年も経過すればほとんど全て2010年以降に作られた秘伝のソースに入れ替わっているはずです。
預貯金もこれと同じように考える裁判官もいるという訳です。
そのため、この場合は、特有財産とされると損をする方が、「合意するぐらいなら裁判官に決めてもらった方がより経済的に有利な解決になる可能性がある」などと考えて、なかなか合意しないことがあります。
5.特有財産にお小遣いは含まれるか
少ないお小遣いでやりくりしている方も多いでしょう。
そのお小遣いをコツコツと貯めていた場合、離婚の際にそれを相手に半分渡さなければならないとなれば、心中穏やかではないかも知れません。
しかしながら、残念ですが、当該お小遣いの原資は夫婦共有財産ですので、お小遣いも夫婦共有財産と考えられています。
つまり、結論としては、お小遣いは財産分与の対象とされることが通常の取り扱いです。
6.特有財産性は一筋縄ではいかない問題

ここまで見てきたように、特有財産性は家庭裁判実務上の取り扱いが定まっていない場合もあり、相手との話し合いも一筋縄ではいかないことも多いです。
また、この記事に記載していないような様々な問題点もあり、実際の離婚調停実務上は、その都度当事者がそれらしい理由に基づいて分与方法を主張し、理論的にはスッキリとしない状況で、手打ち式のように離婚の合意が成立していく例も多いです。
財産分与の金額は、離婚後の生活にも直結する重要な問題です。
特有財産性についてお悩みの場合は、もっと有利な財産分与の計算ができる方法や交渉戦略が見つかるかもしれませんので、一度弁護士に相談して確認しておくことをおすすめします。
レイスター法律事務所では、無料法律相談にて、個別具体的な事情に基づいて、どのような主張が成り立ち得るのか、離婚紛争の全体を踏まえた上でどのように交渉していけば良いかについて、可能な限り具体的にお伝えしていますので、是非ご利用ください。
こちらも読まれています