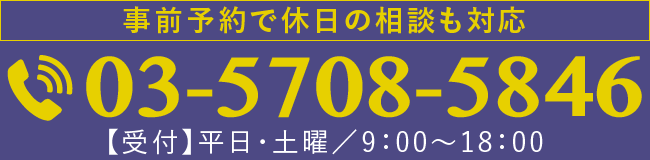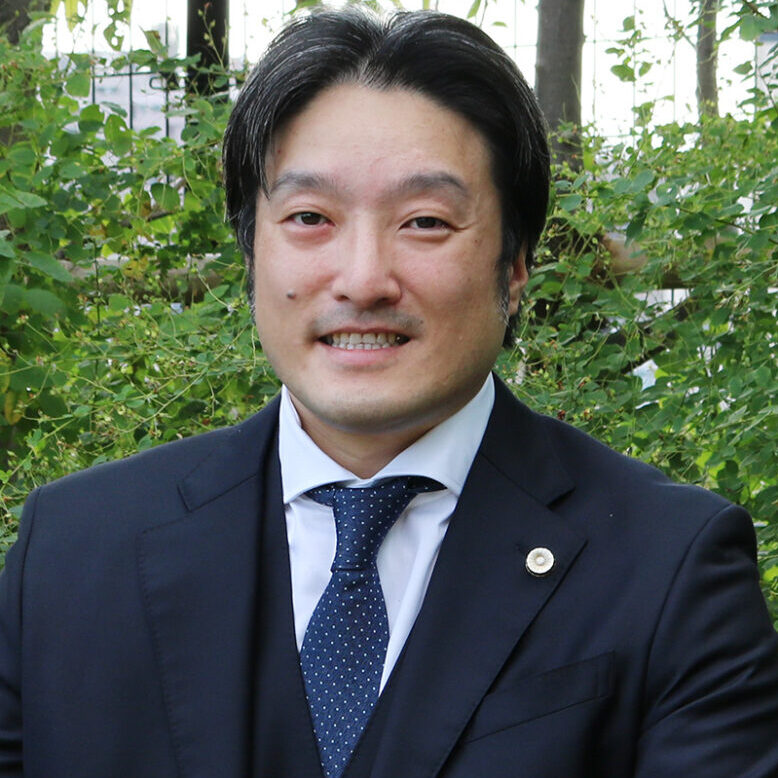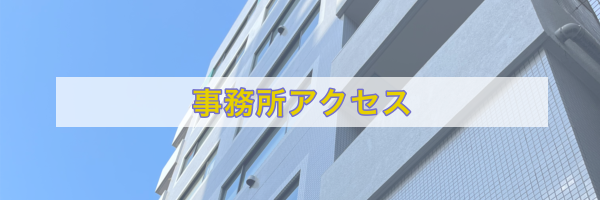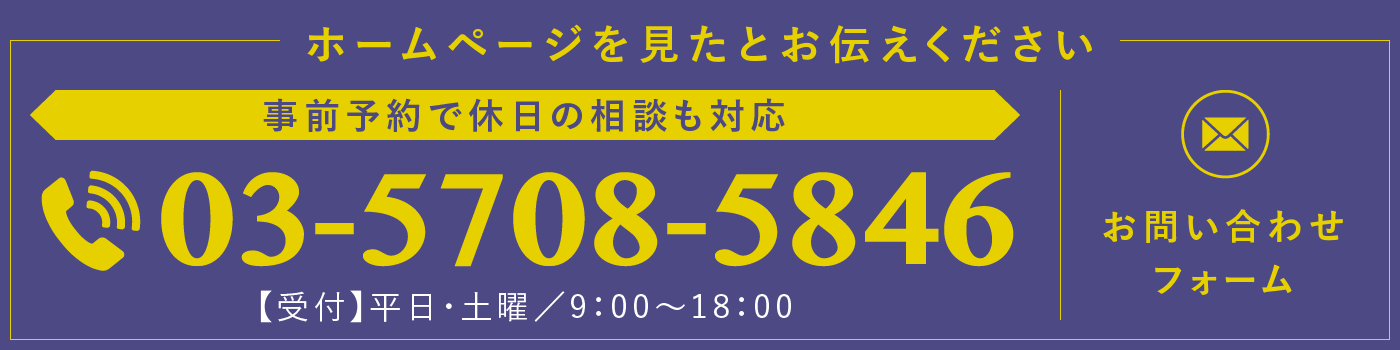更新日:
養育費を離婚した後から請求したいと考えた場合
離婚問題が持ち上がってから離婚が成立するまでの状況は実に様々です。
夫婦で落ち着いて話し合ってお互いが納得した上で離婚を成立させることもありますが、離婚条件についてしっかりとした話し合いがなされないままで離婚の成立に至る例も珍しいことではありません。
養育費についてしっかりと取り決めずに離婚した場合でも、離婚した後から養育費を請求することが可能です。
この記事では、離婚後に養育費を請求する場合の具体的な手続きの流れや、時効などの注意点について解説します。
1.離婚後に養育費を請求することの可否
⑴養育費を決めないでも離婚は成立する

養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことを言います(民法766条、877条)。
離婚する夫婦の間に子どもがいる場合、離婚後の子どもの親権者の取り決めに付随して、養育費の金額が取り決められることが通常です。
ただ、法律上は、離婚に際して絶対に取り決めなければならない離婚条件は親権者だけです。
そのため、離婚する際に養育費に関する事項を取り決めていなかったとしても、離婚は有効に成立します。
⑵離婚後に養育費を請求することはできるか
養育費の根拠は、親の子どもに対する扶養義務にあります。
親は、実の子どもに対して扶養義務を負っています(民法877条1項)。
そして、この親の負う子どもに対する扶養義務は、離婚して子どもの親権を喪失したとしても失われません。
養育費の根拠はこの子どもに対する扶養義務にあり、離婚に際して親権を喪失した方の親も、子どもに対する扶養義務が続く限り、子どもの養育費を支払うべき法律上の義務を負い続けることが原則です。
このことは、離婚の際に養育費に関する事項を取り決めていなかったとしても変わりません。
そのため、離婚の際に養育費に関する事項を取り決めていなかったとしても、離婚後に養育費を請求することは可能です。
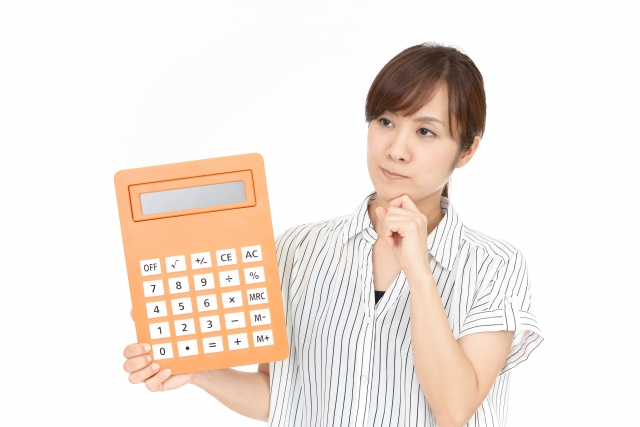
関連記事
2.養育費をさかのぼって支払ってもらうことはできるか
⑴過去分の養育費は請求できないのが原則

家庭裁判実務上は、養育費は、権利者が義務者に対して養育費を請求する意思を明確に示した時から具体的に支払う義務が発生するものと考えられています。
そして、養育費を請求する意思を明確に示す方法としては、口頭で請求するのみでは足りず、書面(内容証明郵便など)で請求することや、養育費請求調停を申し立てることが求められることが多いです。
「養育費を請求する意思を明確に示した時」の具体例
- 内容証明郵便でもって請求した時
- 養育費請求調停を申し立てた時
すなわち、離婚する際に養育費に関する取り決めをしなかった場合は、後から養育費を具体的に請求するまでの間の養育費はもらえなくなってしまいます。
養育費を請求する意思を明確に示した時点より前にさかのぼって請求することができないとされている理由は、養育費はあくまでもそれを請求する権利者の権利であって義務ではない(養育費を請求することも請求しないことも権利者の自由である)という点や、過去分の扶養は原理上あり得ないという点や、養育費の請求を受ける側の過大な金銭的負担に対する配慮などが考えられます。
具体例で説明
・令和元年5月20日に養育費の取り決めをしないで離婚した
⇩
・令和2年5月20日に口頭で養育費を請求したが支払われなかった
⇩
・令和3年5月20日に内容証明郵便で養育費を請求したが支払われなかった
⇩
・令和4月5月20日に養育費請求調停を申し立てて養育費を請求した
⇨養育費は、内容証明郵便により養育費を請求した令和3年5月20日の属する月(令和3年5月分)から具体的に請求できることとなる
離婚時に養育費を取り決めていた場合
離婚する時に養育費の取り決めをしていた場合は、義務者が取り決めた通りの養育費を支払わずに未払いとなっている養育費の金額について、後から一気に請求できることは当然です。
ただし、この場合は、後述するように、時効に注意しましょう。
⑵養育費を請求する意思を明確に示した時点より前にさかのぼって支払ってもらえる場合もある

そもそも養育費の根拠は親の子どもに対する扶養義務(民法877条1項)にあるところであり、親の子どもに対する扶養義務は親権者である最中はもちろん、離婚により親権を喪失したとしてもそのまま継続的に負い続けます。
そのため、離婚する際に養育費の取り決めをしていなかったとしても、子どもに対する扶養義務が存在している状況には変わりはない以上、本来であれば養育費を支払う義務があるとも言えそうです。
裁判例の中にも、裁判所の裁量によって相当と認める範囲内において、具体的に養育費を請求した時点よりも過去にさかのぼって養育費の支払い義務を認めることができると判断しているものもあります(東京高等裁判所決定昭和58年4月28日など)。
ただし、裁判所がこのように養育費の支払い義務を請求した時点より過去にさかのぼって認める例は極めて少数にとどまります。
しかも、その場合でも、離婚した時までさかのぼって認められることは、現在の家庭裁判実務上は、よほど特殊な事情がない限りまずあり得ないと考えられます。
この結論は、婚外子の場合に認知する前の過去の未払養育費の請求が認められる余地があること(大阪高等裁判所決定平成16年5月19日)との対比上アンバランスな気がしなくはないですが、いずれにしても家庭裁判実務上はこのような扱いとなっています。
なお、家庭裁判所は「養育費を請求できるにも関わらず請求していなかったのに今更過去分までまとめて請求することは請求される方にとって酷」という考えを強くもっている様子です。
そのため、このような請求時点よりも過去にさかのぼっての養育費の請求を認めてもらうためには、子どもの生活のために養育費の支払いが必要であるとの事情に加えて、今まで養育費を請求していなかった理由についてしっかりと説明することが必要とされます。
アドバンスな交渉戦略
このように、養育費を請求した時点よりも前にさかのぼって請求することは、家庭裁判実務上は難しい場合も多いです。
ただし、法律上請求することが難しいとしても、相手が支払いに応じるのであれば、過去分にさかのぼって養育費を受け取ることが当然できます。
それに、裁判所も、過去分にさかのぼっての請求を完全に否定しているものではなく、少数ながらさかのぼっての請求が認められ得る余地を残した判断をしています。
そのため、過去分の養育費についても、法律上請求することができないからと諦めるのではなく、まずは相手に請求してみて、相手と話し合ってみることが良いでしょう。
相手としても、子どものための費用については財布の紐が緩い場合もありますので、最初から諦めてしまう必要はありません。
ただ、かといって、相手が支払いを拒否した場合には、過去分の養育費は支払ってもらえなくなってしまう可能性が高いので、そのことを踏まえて、できるだけ早く明確に請求しておくことをおすすめします。
3.義務者に養育費を請求するための具体的な方法
⑴義務者に対して請求して話し合い(協議)をして決める

義務者が養育費の話し合いにしっかりと応じるのであれば、義務者との間で養育費の月額や毎月の支払時期などを話し合って取り決めるのが最もスムーズでしょう。
そして、義務者との間で養育費の月額や終期などの条件について合意が成立した場合には、後から言った言わないの争いとならないためにも、養育費に関する条件を明確に記載した書面を作成して、お互いに署名・押印をして、保管しておくことが重要です。
さらに、養育費に関する取り決めは、可能な限り公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が当事者間で成立した合意の内容を確認した上でそれを記載した書面(公文書)をいいます。
養育費に関する取り決めを公正証書にしておくことにより、相手が養育費を支払わなくなった場合には、プラスαの裁判所における手続(調停・審判・裁判)を経ることなく、強制執行を実施することができるようになります。
強制執行を実施すれば、相手の預貯金口座や所有不動産などの資産を差し押さえてそこから強制的に経済的給付を受けたり、裁判所から相手の勤務先に連絡してもらって相手の給与債権を差し押さえて相手の勤務先から直接経済的給付を受けたりすることができます。
公正証書にはこのような極めて強い効力がありますので、養育費に関する取り決めを公正証書にしておくことにより、相手が取り決めた内容通りの支払いを誠実に実施してくれる可能性が高まる(紛争を未然に防止する)との効果もあります。
⑵養育費請求調停
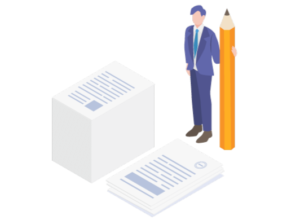
義務者は既に子どもと一緒に生活をしている状況にはありませんので、離婚してから期間が経過すればするほど、人生の必須のパーツとして新たな恋人、新たな配偶者(再婚相手)、新たな子どもが現れ、その分自身の生活の構成要素になっていない元配偶者や子どもに対する興味・関心は薄れていきます。
そのような相手にとっては、養育費を請求してくる元配偶者は招かれざる客なわけです。
そのため、義務者が養育費に関する話し合いに応じてくれなかったり、養育費の金額について不誠実な提案を繰り返してきたりすることもよくある話です。
その場合には、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てて、相手との間で話し合いを進めていくこととなります。
養育費請求調停の期日では、裁判所・調停委員会を間に入れて、養育費の適正な金額などの条件についての話し合いが行われます。
そして、義務者との間で養育費に関して合意が成立すれば、合意内容が調停調書に記載されます。
⑶養育費請求審判
義務者が養育費請求調停の期日に出頭しなかったり、調停期日に出頭しても養育費の支払いや養育費の金額などの条件に関して合意が成立しなかったりした場合には、調停手続は不成立となって終了し、自動的に審判手続に移ることとなります。
審判手続では、家庭裁判所が当事者双方の収入状況などを見て適正な養育費の金額を決定してくれます。
そして、調停調書または審判にて婚姻費用の金額が決定されたにもかかわらず義務者が養育費を支払わない場合には、強制執行を実施して、義務者の預貯金口座や所有不動産などの資産を差し押さえてそこから強制的に養育費の支払いを受けたり、裁判所から義務者の勤務先に連絡してもらって義務者の給与債権を差し押さえて義務者の勤務先から直接養育費の支払いを受けたりすることができます。

関連記事
4.養育費を請求する権利は時効で消滅してしまう
⑴養育費の時効期間

未払いとなっている養育費は義務者に対して一気に請求することができます。
ただし、未払いの養育費を請求せずに放置したままでいると、養育費を請求する権利は時効により消滅してしまいます。
養育費を請求する権利が時効により証明するまでの期間は、支払期日から5年(民法166条1項1号)です。
そのため、養育費の未払いを5年間放置していると、義務者に対して請求することができなくなってしまいます。
ただし、時効期間が経過してしまったとしても、義務者が時効消滅を主張せずに任意に支払ってくれれば問題ないので、諦めずに義務者に請求をしてみましょう。
⑵養育費の時効の完成を阻止する手段
消滅時効の完成を阻止する制度として時効の完成猶予や時効の更新という制度があります(民法147条)。
例えば、養育費請求調停や審判を申し立てたり、養育費を請求する裁判を提起したり、仮差押え・差押えなどの強制執行手続きをしたりすることで、養育費の時効期間はリセットされます。
また、養育費の時効期間が間近に迫っている場合には、取り急ぎ義務者に内容証明郵便などで未払養育費の請求をしておけば、養育費の時効の関係が6か月間猶予されます。
そして、この6か月間の猶予期間のうちに、養育費請求調停の申し立てや強制執行手続きを行うことで、未払いとなっている養育費を回収することが可能です。
未払いとなっている養育費の金額を裁判上の手続きで確定させた場合の時効期間
相手が養育費を支払わないことから、養育費請求調停や審判を申し立てたり、養育費を請求する裁判を提起したりした場合、当該裁判上の手続きを通じて未払いとなっている養育費の総額が確定することとなります。
その場合は、当該未払いとなっている養育費の総額は、その支払期日から10年で時効消滅します(民法169条1項)。
なお、この10年という時効期間は、あくまで調停・審判・裁判で未払いとなっている養育費の金額が決まった場合における、当該未払養育費を請求する権利の消滅時効期間です。
調停・審判・裁判を通じて毎月の養育費の金額が決まった場合における、当該毎月の養育費の時効期間は原則通り支払期日から5年ですので、注意です。
5.養育費は確実に支払ってもらおう

養育費は子どもの生活のために重要な資金源であり、毎月支払いを受けられるものであって、その総額は極めて高額となり得るものです。
レイスター法律事務所では無料法律相談において想定される養育費の具体的な金額や、少しでも有利な金額となるような話し合いの進め方などを詳細にお伝えしていますので、是非ご利用ください。